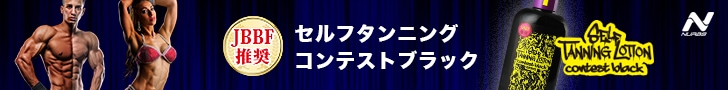◆ボディビルディングの革命理論<その10>◆
筋力トレーニングの要因
月刊ボディビルディング1979年11月号
掲載日:2018.09.19
国立競技場指導係主任 矢野雅知
前回は、バルクとパワーの獲得において、筋肉をつくりあげる理論的に最も早いルーティーンについて述べた。それには、どのレピティションでも、できるだけハードに、しかもできるだけ多くのレップスをやるように強調してきた。そして、セット間、ならびにエクササイズ間のインターバルは最小にとどめ、ボディ・パート間のインターバルは、疲労物質のセオリーから十分長くとるようにも述べた。
さて、筋肉が増量すれば、いずれは1000ポンド(約453kg)のベンチ・プレスも記録されるだろう。不可能とされた600ポンド(約272kg)のクリーン&ジャークのカベは、すでにアレキセーエフによって破られているし、今後もさらに偉大な挙上記録が樹立されていくにちがいない。
今回は、この大きな「筋力」をつくりあげることについて、まとめていきたいと思う。
リフティングにおいて、大きな筋力を発揮するということは、リフティングのテクニックは度外視して、筋肉のサイズに見合った筋力以上の力を出すということは、理論的に言ってかなり複雑なファクターが介在してくる。筋肉のサイズを獲得するには疲労物質が関連するが、大きな筋力を発揮することには、神経システムが大きく関与してくる。
わかりやすい例として、初心者がウェイトを持ち挙げることを考えてみよう。ベンチ・プレスで最大重量に挑んでみると、初心者の筋肉のサイズ先天的な筋肉と骨格とのテコの作用によって、ある重量までは持ち挙げることができる。そして、これを何度もくり返していくうちに、筋肉と神経の相互の関連が高まってきて、筋肉のサイズが増加していなくても、最大重量が20%以上もアップすることがある。このことは誰でも一度は体験しているのではないだろうか。これは筋肉の増加というよりも、彼の挙上能力が増加したと考えられる。
このように、筋力は、外見に現れてこなくても、いくつかのファクターに影響されているのである。
さて、筋肉が増量すれば、いずれは1000ポンド(約453kg)のベンチ・プレスも記録されるだろう。不可能とされた600ポンド(約272kg)のクリーン&ジャークのカベは、すでにアレキセーエフによって破られているし、今後もさらに偉大な挙上記録が樹立されていくにちがいない。
今回は、この大きな「筋力」をつくりあげることについて、まとめていきたいと思う。
リフティングにおいて、大きな筋力を発揮するということは、リフティングのテクニックは度外視して、筋肉のサイズに見合った筋力以上の力を出すということは、理論的に言ってかなり複雑なファクターが介在してくる。筋肉のサイズを獲得するには疲労物質が関連するが、大きな筋力を発揮することには、神経システムが大きく関与してくる。
わかりやすい例として、初心者がウェイトを持ち挙げることを考えてみよう。ベンチ・プレスで最大重量に挑んでみると、初心者の筋肉のサイズ先天的な筋肉と骨格とのテコの作用によって、ある重量までは持ち挙げることができる。そして、これを何度もくり返していくうちに、筋肉と神経の相互の関連が高まってきて、筋肉のサイズが増加していなくても、最大重量が20%以上もアップすることがある。このことは誰でも一度は体験しているのではないだろうか。これは筋肉の増加というよりも、彼の挙上能力が増加したと考えられる。
このように、筋力は、外見に現れてこなくても、いくつかのファクターに影響されているのである。
<1>筋繊維のサイズ
トレーニングによって筋肉を太くするということは、ほとんどの人が挙上能力を大きくするためのベストのものと理解しているものである。
たしかに、筋力そのものは、筋肉の生理的横断面積に比例するのであるから、筋肉が大きいほど大きな筋力を発揮できるようになる。しかしながら、次のようなことが指摘されなくてはならない。
筋繊維は、筋肉の実際の収縮をつかさどる筋源繊維、すなわち収縮筋と、新陳代謝をつかさどったり、エネルギーを供給したりするといった補助的な役割を果たす筋形質とから構成される。そして、収縮筋のサイズが大きくなるほど筋力は増大することになる。
一方、筋形質が大きくなるほど持久力が高まって、疲労物質の耐性も高まってくるが、これは筋肉の収縮能力にはほとんど関係しないので、筋形質のサイズの増大は、筋力に直接影響を及ぼさない。
たしかに、筋力そのものは、筋肉の生理的横断面積に比例するのであるから、筋肉が大きいほど大きな筋力を発揮できるようになる。しかしながら、次のようなことが指摘されなくてはならない。
筋繊維は、筋肉の実際の収縮をつかさどる筋源繊維、すなわち収縮筋と、新陳代謝をつかさどったり、エネルギーを供給したりするといった補助的な役割を果たす筋形質とから構成される。そして、収縮筋のサイズが大きくなるほど筋力は増大することになる。
一方、筋形質が大きくなるほど持久力が高まって、疲労物質の耐性も高まってくるが、これは筋肉の収縮能力にはほとんど関係しないので、筋形質のサイズの増大は、筋力に直接影響を及ぼさない。
<2>筋肉へ電気的エネルギーを伝える大きさの変化
ピアリー・レイダー氏によって「神経力」と名づけられたように、インパルスの強さは常に一定しているものではなくて、脳からのメッセージにより大きくなったり小さくなったりするかも知れないのである。
筋肉と神経との付着部の運動終板は神経のインパルスをより強く、あるいは弱く保つ能力をもつ。それゆえ「全か無かの法則」に従って筋肉が収縮しているのは事実であるけれども、それがすべてに当てはまらないかもしれない。筋肉の収縮力は神経力の大きさに左右されるのかもしれないのである。
筋肉と神経との付着部の運動終板は神経のインパルスをより強く、あるいは弱く保つ能力をもつ。それゆえ「全か無かの法則」に従って筋肉が収縮しているのは事実であるけれども、それがすべてに当てはまらないかもしれない。筋肉の収縮力は神経力の大きさに左右されるのかもしれないのである。
<3>神経衝撃(インパルス)の頻度の向上
神経は各筋線維に一定のリズムでインパルスを送る。だから、筋線維は1秒間に幾度も収縮とリラックスをくり返していることになる。今、軽いウェイトを持ち挙げようとするとき、筋線維には毎秒12インパルスが送られるとしよう。ところが、最大負荷を持ち挙げようとすると、毎秒50インパルスにもはねあがる。インパルスの頻度が極度に高まると、筋肉の緊張は最も強くなり、リラックスする暇がなくなって、緊張しっぱなしになる。
だが、インパルスの頻度が増加すれば、筋肉の緊張度も大きくなるので、同じ大きさの筋肉でもより大きな筋力を発揮することができる。
我々は長いこと、毎秒50インパルスというのが、筋肉を緊張させるものの最高の衝撃である、と考えてきた。しかし、高度に鍛錬された競技者のなかには、瞬時にして爆発的なそれ以上のインパルスを生じることができる。ということが実験によって確かめられた。このことは、同じ大きさの筋肉であっても、より大きな筋力を発揮することができることを意味している。
だが、インパルスの頻度が増加すれば、筋肉の緊張度も大きくなるので、同じ大きさの筋肉でもより大きな筋力を発揮することができる。
我々は長いこと、毎秒50インパルスというのが、筋肉を緊張させるものの最高の衝撃である、と考えてきた。しかし、高度に鍛錬された競技者のなかには、瞬時にして爆発的なそれ以上のインパルスを生じることができる。ということが実験によって確かめられた。このことは、同じ大きさの筋肉であっても、より大きな筋力を発揮することができることを意味している。
<4>神経と筋肉のコーディネーション
さきに述べたように、初心者において、筋肉の肥大を伴わないのに、筋力が増加することを、これによって説明することができる。
<5>腱の力
パワーを生み出すのは、筋肉の収縮だけである、いかに腱が強くても、骨格が頑丈にできていいても、そんなことはパワーには関係ない。つまり、筋肉の発揮するパワーを出すことはできないのである。
しかしながら筋肉は、骨格や腱からなる支持構造(サポーティング構造)を超えるような力を発揮することはできない。そんなことができたら、骨や腱がちぎれたり、折れたりしてしまうからである。ただ、たとえ挙上できないような重いウェイトであっても、サポーティング構造でこれを保持することはできる。
たとえば、ベンチ・プレスで両腕を伸ばした姿勢なら、最大負荷を超えたウェイトでもガッチリ支えられるし、スクワットでも、しゃがめないほどの重量であっても、背中にかついで立つことはできる。スタンディング・プレスでも、頭上に差し挙げられなくても肩に保持することはできるであろう。これはすべて腱が筋肉よりも強く、しかも骨格で固定できるからである。
筋肉の発揮するパワーを超える力にも、このサポーティング構造は対応できるのであるから、いずれにしても腱が強いということは、最大筋力を高めていくうえで、1つのファクターとなる。それはまた、最大負荷以上のものであっても扱えるという、精神的メリットも大きなものがある。
しかしながら筋肉は、骨格や腱からなる支持構造(サポーティング構造)を超えるような力を発揮することはできない。そんなことができたら、骨や腱がちぎれたり、折れたりしてしまうからである。ただ、たとえ挙上できないような重いウェイトであっても、サポーティング構造でこれを保持することはできる。
たとえば、ベンチ・プレスで両腕を伸ばした姿勢なら、最大負荷を超えたウェイトでもガッチリ支えられるし、スクワットでも、しゃがめないほどの重量であっても、背中にかついで立つことはできる。スタンディング・プレスでも、頭上に差し挙げられなくても肩に保持することはできるであろう。これはすべて腱が筋肉よりも強く、しかも骨格で固定できるからである。
筋肉の発揮するパワーを超える力にも、このサポーティング構造は対応できるのであるから、いずれにしても腱が強いということは、最大筋力を高めていくうえで、1つのファクターとなる。それはまた、最大負荷以上のものであっても扱えるという、精神的メリットも大きなものがある。
<6>からだのコンディションが筋力に影響する
「全か無かの法則」に従って、そのとき働く筋繊維は、最大の収縮をして最大のパワーを発揮するが、からだのコンディションによって、より大きくあるいはより小さく収縮することも考えられる。
一例をあげると、酸素の供給が十分なところでは、より強く収縮するから大きな筋力を出すが、酸素の供給が十分ではないところでは、大きな筋力を出しえないことになる。
一例をあげると、酸素の供給が十分なところでは、より強く収縮するから大きな筋力を出すが、酸素の供給が十分ではないところでは、大きな筋力を出しえないことになる。
<7>最大筋力の発揮は、精神力によって大きく反応する。
自分では最大の筋力を出しているつもりであっても、精神のあり方ひとつで、さらにそれ以上の筋力を発揮するということもよくあることだ。
大声援を受ければ、誰でも実力以上の力を出すものだし、クレストウニコフの研究で、音楽が筋力を向上させることが知られている。軍艦マーチを聞きながら行えば、恐らく筋力は向上するであろう。
また、カルポビッチと故猪飼教授の研究で、催眠も筋力を向上させることが証明されている。そのほか、最大筋力を測定中に、とび抜けたベッピンが現れたとたん、たちまち新記録が生まれたというように、精神が筋力に及ぼす力は大きいといえよう。
なかでも、極度の興奮状態に陥ったときに発揮するパワーは、信じがたいほどのものがある。子供がクルマの下敷きになろうとしたとき、母親がすっ飛んできてクルマをひっくり返してしまったという例がある。これは、いわゆる”火事場のバカ力”であるが、このバカ力が意識して発揮できれば、スキルや運動の正確度は乱れるようになるが、とてつもない記録をつくることが可能であろう。
催眠実験では、最大筋力の30%ほど向上させられたという例もあり、我々が通常考えている限界よりも、筋力の潜在的な大きさは、その3倍はあるように思われる。
マイク・デイトンは「Chi(気)」の論文において、この潜在力をも引き出して、偉大な筋力を発揮する精神パワーを用いるという概念を述べている。フランコ・コロンブにしても同様である。すべての偉大なる力技チャンピオンたちはこのことをよく知っている。マイク・デイトンが述べているほどのレベルではないにしても、精神のパワーを十二分に活用しているのは事実である。
忘れてはならないことは、精神のパワーは、筋肉ではなく、筋肉を働かせる神経システムに直接影響するということである。
大声援を受ければ、誰でも実力以上の力を出すものだし、クレストウニコフの研究で、音楽が筋力を向上させることが知られている。軍艦マーチを聞きながら行えば、恐らく筋力は向上するであろう。
また、カルポビッチと故猪飼教授の研究で、催眠も筋力を向上させることが証明されている。そのほか、最大筋力を測定中に、とび抜けたベッピンが現れたとたん、たちまち新記録が生まれたというように、精神が筋力に及ぼす力は大きいといえよう。
なかでも、極度の興奮状態に陥ったときに発揮するパワーは、信じがたいほどのものがある。子供がクルマの下敷きになろうとしたとき、母親がすっ飛んできてクルマをひっくり返してしまったという例がある。これは、いわゆる”火事場のバカ力”であるが、このバカ力が意識して発揮できれば、スキルや運動の正確度は乱れるようになるが、とてつもない記録をつくることが可能であろう。
催眠実験では、最大筋力の30%ほど向上させられたという例もあり、我々が通常考えている限界よりも、筋力の潜在的な大きさは、その3倍はあるように思われる。
マイク・デイトンは「Chi(気)」の論文において、この潜在力をも引き出して、偉大な筋力を発揮する精神パワーを用いるという概念を述べている。フランコ・コロンブにしても同様である。すべての偉大なる力技チャンピオンたちはこのことをよく知っている。マイク・デイトンが述べているほどのレベルではないにしても、精神のパワーを十二分に活用しているのは事実である。
忘れてはならないことは、精神のパワーは、筋肉ではなく、筋肉を働かせる神経システムに直接影響するということである。
<8>筋肉それ自身に変化が起きるかもしれない
これについては、かなり難解なので、簡単に述べることにする。
収縮筋には、ミオシン、アクチンといった筋源繊維があり、両者の働きで筋肉の収縮が生じているわけだが、そのメカニズムは、まだ完全に解明されていない。しかし、次のような仮説が考えられるかもしれない。
ミオシンとアクチンの両者のつながりが、トレーニングによって収縮を起こしやすいように変化して、より効果的なものとなる。その結果、筋肉の大きさは変化しないのに、より大きなパワーを生み出せるようになる。
このことは、かなり高度に鍛錬されたリフターの筋肉に起るように思われる。
され、以上のように、筋力を左右するファクターをいくつか挙げたが、いままで述べてきたように、筋力を向上させるには、筋肉自体を鍛錬することと同時に、神経システムを向上させるための適切なトレーニングがなされなくてはならない。では、どういった種類のトレーニング・システムが、このためのベストなものとなるのであろうか?
残念なことには、我々は筋力を増加するベストの方法を見い出すことよりも、太くて大きい筋肉をつくるためのベストの方法を理解することの方に専心している。
前回の「バルクとパワー・アップの要約」において、偉大なる筋量を獲得するのにベストであると考えられるサンプル・ルーティーンを示すことができた。
しかし、リフティングにおける偉大な筋力を獲得するための、決定的と考えられるようなルーティーンを示すことはできない。恐らくこうすればよかろうという推察はできるのだが、実際の場における根拠となりうる「事実」を、さらに必要としている。
最大のバルクを獲得することが、最大のストレングス(筋力)を生み出すことに直結しない、ということは明らかにされている。つまり、筋力は、筋肉のサイズだけでなく、テコ作用、神経の支配する力など、多くの要因が影響してくるからである。
たとえば、やったことのない種目のリフティングの練習をすると、筋肉のサイズは増加しなくても、挙上能力が向上して重いものを扱えるようになってくるが、そういった効果を与えるためには、どういった種類のトレーニングがベストのものになるのか?さらに研究が進めば、おそらく現在とは違った新しい効果的なトレーニング法が見い出せるかもしれない。
我々は21世紀のパワーリフターたちが、果たしてどういったトレーニングを行うであろうか、正確なことはわからないが、たぶんこうなるであろう、という1つの方向づけは指摘することができる、
上記のファクターのすべては、ヘビー・ウェイトによるロー・レップスのハードなトレーニングによって、ある期間以上にわたって発達させることができたといえば、筋力を増大させるにはこれですべてOKと考えるかもしれないが、それだけではまだ十分ではないであろう。しかし、この点については1つだけ確かな論拠がある。
それは、このシリーズ(2)で説明したように、ヘビー・ウェイトによるロー・レップスのトレーニングは、筋肉の収縮する部分(収縮筋)にとくに効果があり、ハイ・レップスでのトレーニングは、筋収縮のエネルギーを生み出す筋形質により効果的である。したがって、筋力を増大させるためには、収縮筋を発達させなくてはならないのだから、ヘビー・ウェイトでやらなくてはならないのは明確である。
では、そのトレーニングはどのくらいの量を行うのがベストなのであろうか?最適のレピティションとは?休息はどれくらいが最適なのか?年齢によってトレーニング法を変えるべきか?といったような疑問が当然ある。
ビルダーの中には、同一筋群に対して、ほとんど毎日のように最大の緊張を強いるトレーニングが最適という人がいる。また、1つの筋肉に対して、1週間に一度だけ最大の緊張を与えるトレーニングが最適という人もいる。こういった極端なタイプは別として、通常のレベルでは次のようなことが言えるのではないだろうか。
すなわち、25歳以下であるなら、各筋群のトレーニングは1週間に3回やるのがよい。25歳以上であるなら、これを週2回にする。これは、一般的に20代半ば頃から新陳代謝の能力が低下しはじめるからである。
人によっては代謝活動がまだまだ盛んだからと、30代、40代になっても連日ハードなトレーニングをやることができるかもしれない。しかし、その能力は必ず低下してくるものであるから「オレはまだ若いんだから……」と過信していると、どこかで破綻をきたすことになるやもしれぬ。
フランク・ゼーンは、ダブル・スプリット・ルーティーンは長い期間にわたって続けるべきではない、と指摘しているが、このことからも、それがきわめて有益なアドバイスであることがわかる。
一般に、リフターにとってのロー・レップスとは、1~5回くらいを指しているが、ベンチ・プレスやスクワットのような基礎種目でのリフティングでは、5~6回前後がベストであると考えられている。言うまでもなく、それは1回ごとに最大の力を発揮することが必要であるが、それができるようになるには、かなりの修練がいる。
また、中には、一般のリフターよりも大きなレベルまで、こういったルーティーンで彼の持てるエネルギーのすべてを完全につ使いつくす能力を持っている人がいる。だが、「過ぎたるは及ばざるが如し」であって、全エネルギーをトレーニングで出しきってしまえば、オーバー・ワークに陥ってしまう危険性もある。
トレーニングの「最適の量」は、筋肉に最大の刺激を与える「最も少ない量」である。それゆえ、からだのエネルギーの多くは、回復、維持に用いられるから、効率よく筋肉は発達していくのである。
セット間の休息についても同様である。最大の筋力を発揮するためには、神経が大きく関与してくるので、神経システムが十分に機能できる状態にしておかなければならない。そのためには、呼吸が通常のレベルに回復するまで休まなくてはならないが、そうかといって必要以上に休むべきではない。(つづく)
収縮筋には、ミオシン、アクチンといった筋源繊維があり、両者の働きで筋肉の収縮が生じているわけだが、そのメカニズムは、まだ完全に解明されていない。しかし、次のような仮説が考えられるかもしれない。
ミオシンとアクチンの両者のつながりが、トレーニングによって収縮を起こしやすいように変化して、より効果的なものとなる。その結果、筋肉の大きさは変化しないのに、より大きなパワーを生み出せるようになる。
このことは、かなり高度に鍛錬されたリフターの筋肉に起るように思われる。
され、以上のように、筋力を左右するファクターをいくつか挙げたが、いままで述べてきたように、筋力を向上させるには、筋肉自体を鍛錬することと同時に、神経システムを向上させるための適切なトレーニングがなされなくてはならない。では、どういった種類のトレーニング・システムが、このためのベストなものとなるのであろうか?
残念なことには、我々は筋力を増加するベストの方法を見い出すことよりも、太くて大きい筋肉をつくるためのベストの方法を理解することの方に専心している。
前回の「バルクとパワー・アップの要約」において、偉大なる筋量を獲得するのにベストであると考えられるサンプル・ルーティーンを示すことができた。
しかし、リフティングにおける偉大な筋力を獲得するための、決定的と考えられるようなルーティーンを示すことはできない。恐らくこうすればよかろうという推察はできるのだが、実際の場における根拠となりうる「事実」を、さらに必要としている。
最大のバルクを獲得することが、最大のストレングス(筋力)を生み出すことに直結しない、ということは明らかにされている。つまり、筋力は、筋肉のサイズだけでなく、テコ作用、神経の支配する力など、多くの要因が影響してくるからである。
たとえば、やったことのない種目のリフティングの練習をすると、筋肉のサイズは増加しなくても、挙上能力が向上して重いものを扱えるようになってくるが、そういった効果を与えるためには、どういった種類のトレーニングがベストのものになるのか?さらに研究が進めば、おそらく現在とは違った新しい効果的なトレーニング法が見い出せるかもしれない。
我々は21世紀のパワーリフターたちが、果たしてどういったトレーニングを行うであろうか、正確なことはわからないが、たぶんこうなるであろう、という1つの方向づけは指摘することができる、
上記のファクターのすべては、ヘビー・ウェイトによるロー・レップスのハードなトレーニングによって、ある期間以上にわたって発達させることができたといえば、筋力を増大させるにはこれですべてOKと考えるかもしれないが、それだけではまだ十分ではないであろう。しかし、この点については1つだけ確かな論拠がある。
それは、このシリーズ(2)で説明したように、ヘビー・ウェイトによるロー・レップスのトレーニングは、筋肉の収縮する部分(収縮筋)にとくに効果があり、ハイ・レップスでのトレーニングは、筋収縮のエネルギーを生み出す筋形質により効果的である。したがって、筋力を増大させるためには、収縮筋を発達させなくてはならないのだから、ヘビー・ウェイトでやらなくてはならないのは明確である。
では、そのトレーニングはどのくらいの量を行うのがベストなのであろうか?最適のレピティションとは?休息はどれくらいが最適なのか?年齢によってトレーニング法を変えるべきか?といったような疑問が当然ある。
ビルダーの中には、同一筋群に対して、ほとんど毎日のように最大の緊張を強いるトレーニングが最適という人がいる。また、1つの筋肉に対して、1週間に一度だけ最大の緊張を与えるトレーニングが最適という人もいる。こういった極端なタイプは別として、通常のレベルでは次のようなことが言えるのではないだろうか。
すなわち、25歳以下であるなら、各筋群のトレーニングは1週間に3回やるのがよい。25歳以上であるなら、これを週2回にする。これは、一般的に20代半ば頃から新陳代謝の能力が低下しはじめるからである。
人によっては代謝活動がまだまだ盛んだからと、30代、40代になっても連日ハードなトレーニングをやることができるかもしれない。しかし、その能力は必ず低下してくるものであるから「オレはまだ若いんだから……」と過信していると、どこかで破綻をきたすことになるやもしれぬ。
フランク・ゼーンは、ダブル・スプリット・ルーティーンは長い期間にわたって続けるべきではない、と指摘しているが、このことからも、それがきわめて有益なアドバイスであることがわかる。
一般に、リフターにとってのロー・レップスとは、1~5回くらいを指しているが、ベンチ・プレスやスクワットのような基礎種目でのリフティングでは、5~6回前後がベストであると考えられている。言うまでもなく、それは1回ごとに最大の力を発揮することが必要であるが、それができるようになるには、かなりの修練がいる。
また、中には、一般のリフターよりも大きなレベルまで、こういったルーティーンで彼の持てるエネルギーのすべてを完全につ使いつくす能力を持っている人がいる。だが、「過ぎたるは及ばざるが如し」であって、全エネルギーをトレーニングで出しきってしまえば、オーバー・ワークに陥ってしまう危険性もある。
トレーニングの「最適の量」は、筋肉に最大の刺激を与える「最も少ない量」である。それゆえ、からだのエネルギーの多くは、回復、維持に用いられるから、効率よく筋肉は発達していくのである。
セット間の休息についても同様である。最大の筋力を発揮するためには、神経が大きく関与してくるので、神経システムが十分に機能できる状態にしておかなければならない。そのためには、呼吸が通常のレベルに回復するまで休まなくてはならないが、そうかといって必要以上に休むべきではない。(つづく)
月刊ボディビルディング1979年11月号
Recommend
-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!
- BESTBODY JAPAN
- BESTBODY JAPAN Vol.2
- 金額: 1,527 円(税込)
-