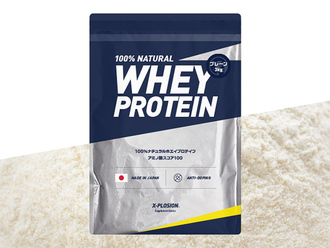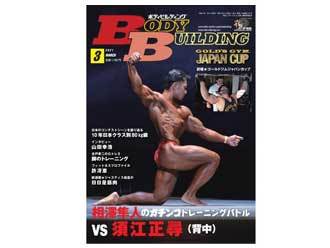大会出場のためのピークウィークセミナー IFBB審査委員会執行役員ホセ マリア ガルシア(Jose Maria García)氏講演
掲載日:2025.04.18

2025年3月23日、IFBB審査委員会執行役員ホセ マリア ガルシア(Jose Maria García)氏による講演「大会出場のためのピークウィークセミナー」が浅草橋にて行われた。
最高の仕上がりで大会当日を迎えるために大会前の一週間をどう過ごすべきかを解説した選手必見の講演をハイライトでレポート。
取材・文 せきぐち
最高の仕上がりで大会当日を迎えるために大会前の一週間をどう過ごすべきかを解説した選手必見の講演をハイライトでレポート。
取材・文 せきぐち
【目次】
・ピークウィークの概要と背景
・ピークウィークの賛否とリスク
・コンテストの準備期間
・体内の水分量の調節
・薄い皮膚のために
・女性の場合
・塩とカーボに関して
・ナトリウム/カリウムの摂取
・最大限のグリコーゲン量を貯蔵するために
・大会前日の食事に関して
・大会当日
・最後に
・ピークウィークの概要と背景
・ピークウィークの賛否とリスク
・コンテストの準備期間
・体内の水分量の調節
・薄い皮膚のために
・女性の場合
・塩とカーボに関して
・ナトリウム/カリウムの摂取
・最大限のグリコーゲン量を貯蔵するために
・大会前日の食事に関して
・大会当日
・最後に
昨日行われた審査員/コーチ向けの講演ではガイノやタトゥー、肩のシンソールなどのイレギュラーラインに関して詳しくお伝えしました。内容の振り返りも兼ねて各カテゴリーでの特徴を再確認しておきましょう。
メンズフィジークでは筋肉量やサイズは主な要素にならず
腰が細く肩が広いプロポーションや腹筋の見え方が重要視されます。
コンディションも大事ですがプロポーションの方が優先されます。筋肉量が多すぎても減点の対象になります。
ボディフィットネスでは丸みを帯びた脚、細い腰、広い肩によるアウトラインが作る「X」シルエットがポイントになります。コンディションの差よりはアウトラインが大事で、これらの点はメンズフィジークに似ていると言えます。
女性に人気があるのはビキニカテゴリー。メイクや表情、立ち居振る舞いも評価に入ります。筋肉量やコンディションに上限があり、過度なものは減点対象になります。
ウェルネスにおいて重要なのは、まずカテゴリーのコンセプトに合った選手が出場すること。筋肉量の65%が下半身、35%が上半身にあることが求められます。
上半身はビキニカテゴリーに近いものが理想的な評価対象ですが、他のどのカテゴリーよりも下半身の筋量が求められます。審査ではまず下半身の筋量を見て、カテゴリに合わないと判断したときには最下位をつけることもあります。
フィットモデルは50%は体を、50%は着衣の状態を評価します。ビキニと同じ基準ではなく「ジムでしっかりとトレーニングをしている」くらいの体型で大丈夫です。しかしあまりにも痩せすぎていたり、多くの脂肪が残る状態ではいけません。メイクや表情、立ち居振る舞いなどの華美さも評価基準に入ります。
メンズフィジークでは筋肉量やサイズは主な要素にならず
腰が細く肩が広いプロポーションや腹筋の見え方が重要視されます。
コンディションも大事ですがプロポーションの方が優先されます。筋肉量が多すぎても減点の対象になります。
ボディフィットネスでは丸みを帯びた脚、細い腰、広い肩によるアウトラインが作る「X」シルエットがポイントになります。コンディションの差よりはアウトラインが大事で、これらの点はメンズフィジークに似ていると言えます。
女性に人気があるのはビキニカテゴリー。メイクや表情、立ち居振る舞いも評価に入ります。筋肉量やコンディションに上限があり、過度なものは減点対象になります。
ウェルネスにおいて重要なのは、まずカテゴリーのコンセプトに合った選手が出場すること。筋肉量の65%が下半身、35%が上半身にあることが求められます。
上半身はビキニカテゴリーに近いものが理想的な評価対象ですが、他のどのカテゴリーよりも下半身の筋量が求められます。審査ではまず下半身の筋量を見て、カテゴリに合わないと判断したときには最下位をつけることもあります。
フィットモデルは50%は体を、50%は着衣の状態を評価します。ビキニと同じ基準ではなく「ジムでしっかりとトレーニングをしている」くらいの体型で大丈夫です。しかしあまりにも痩せすぎていたり、多くの脂肪が残る状態ではいけません。メイクや表情、立ち居振る舞いなどの華美さも評価基準に入ります。
ピークウィークの概要と背景
以前私がジムのオーナーだった時、パーソナルトレーナーを対象とした指導をしていましたがボディビル競技に特化したコーチングを始め、その内容を本にまとめました。
当時はボディビル競技のコンディションに特化した本はなく情報の入手が難しい状況でした。最近でも世界中を探してもそこだけに特化した本は少ないのではないかと思います。それとも日本ではそういう代表作が出回っていますでしょうか。
多くのコーチや選手と相談しながら私自身も多くのコンテストに出場し、ジャッジの実績を重ねながらそれらの知見を集約しました。ピークウィークのプロトコルを完成させる前には、なぜそうなるかを科学的根拠に基づいて求めていきました。
他の国では別の方法が取られることもあるかと思いますが、その場合は各々の選手の過去の経験に基づいているのではないでしょうか。
当時はボディビル競技のコンディションに特化した本はなく情報の入手が難しい状況でした。最近でも世界中を探してもそこだけに特化した本は少ないのではないかと思います。それとも日本ではそういう代表作が出回っていますでしょうか。
多くのコーチや選手と相談しながら私自身も多くのコンテストに出場し、ジャッジの実績を重ねながらそれらの知見を集約しました。ピークウィークのプロトコルを完成させる前には、なぜそうなるかを科学的根拠に基づいて求めていきました。
他の国では別の方法が取られることもあるかと思いますが、その場合は各々の選手の過去の経験に基づいているのではないでしょうか。
ピークウィークの賛否とリスク
まず、最初にお伝えしたいのはピークウィークを取り入れる必要性があるかを自身でよく考えることです。事前に十分な仕上がりにできたと思うのであれば、ピークウィークを取り入れる必要はありません。
個人的には、2~3週間前に理想的な仕上がりになっていればピークウィークを取り入れなくても良いと考えています。ピークウィークはリスクも含みます。それでもやるならばという選手に対してのプロトコルです。
繰り返しますが、十分に仕上がっているのであればやる必要はありません。ビタミンやミネラル、水分が体内に十分にない状態を長期間続けることでピークウィークがうまくいかない可能性もあります。
大会の少し前までは良いコンディションでも、大会が近づいたときに大きく崩れる選手もいます。なぜでしょうか。ピークウィークの過ごし方が良くなかったからです。ビタミンやミネラル、ホルモンの分泌などに問題があったと考えられます。
個人的には、2~3週間前に理想的な仕上がりになっていればピークウィークを取り入れなくても良いと考えています。ピークウィークはリスクも含みます。それでもやるならばという選手に対してのプロトコルです。
繰り返しますが、十分に仕上がっているのであればやる必要はありません。ビタミンやミネラル、水分が体内に十分にない状態を長期間続けることでピークウィークがうまくいかない可能性もあります。
大会の少し前までは良いコンディションでも、大会が近づいたときに大きく崩れる選手もいます。なぜでしょうか。ピークウィークの過ごし方が良くなかったからです。ビタミンやミネラル、ホルモンの分泌などに問題があったと考えられます。
コンテストの準備期間

ピークウィークの前に、コンテストの準備として数か月の減量期間があります。その期間を2つのフェーズに分けて考えます。
①プレコンペティション
この期間では脂肪を落としつつも筋肉を保つこと。
②ピークウィーク
皮膚を薄くすることと筋内にグリコーゲンを貯蔵すること。
ボディビルの大会では皮膚が薄い方が筋がよく見え、皮膚が厚いと筋は見えにくくなります。一方で筋を大きく見せるためには筋にグリコーゲンを貯蔵しておくことが大切です。
①プレコンペティション
この期間では脂肪を落としつつも筋肉を保つこと。
②ピークウィーク
皮膚を薄くすることと筋内にグリコーゲンを貯蔵すること。
ボディビルの大会では皮膚が薄い方が筋がよく見え、皮膚が厚いと筋は見えにくくなります。一方で筋を大きく見せるためには筋にグリコーゲンを貯蔵しておくことが大切です。
体内の水分量の調節
多くの選手は大会前に人生で一番水分量を減らそうとしますが、水分が細胞内に入ることが重要です。
ドライであればあるほど良いと思うかもしれませんが、水分をカットすると体はより多くの水分を欲するようになります。そのため、その性質を応用して真逆の事をやります。超回復の原理を応用して体内の水分量を調節するのです。体は問題に対して適応して解決しようとします。
単純に水分をカットする古典的な方法では大会当日はドライにできますが、大会が終わった後には非常にむくみます。例えば1週間後に大会が控えている場合にはコンディションを整えることが難しいため推奨はしません。
ドライであればあるほど良いと思うかもしれませんが、水分をカットすると体はより多くの水分を欲するようになります。そのため、その性質を応用して真逆の事をやります。超回復の原理を応用して体内の水分量を調節するのです。体は問題に対して適応して解決しようとします。
単純に水分をカットする古典的な方法では大会当日はドライにできますが、大会が終わった後には非常にむくみます。例えば1週間後に大会が控えている場合にはコンディションを整えることが難しいため推奨はしません。
薄い皮膚のために
皮膚を薄くしてむくみをなくすことを狙います。
脂肪組織は減量で薄くなりますが、そこからさらに薄くするためにピークウィークで水分を調節します。男女で量に差はありますがやることとしてはほぼ同じです。
ここで重要なのは必要以上の水分を摂取することです。一週間前ほどから非常に多くの水分を摂取し、大会当日に近づくにつれて水分の摂取量を減らしていきます。
必要以上の水分は体にダメージになりますが、体はそれを体外に排出していく機能があります。日本の気候を考えてもこれくらいになるかと思います。
特に最初の数日は摂った水分以上の水を排出しようとするため体は水を溜め込もうとしなくなります。
利尿作用のあるアスパラ、パインなどの果物やビタミンCやBを摂ることも有効です。
大会当日の土曜日は必要に応じて、のどが乾いたら飲む程度に摂取します。後述しますが木曜日からはカーボローディングと並行します。カーボローディングには水分も必要になります。
脂肪組織は減量で薄くなりますが、そこからさらに薄くするためにピークウィークで水分を調節します。男女で量に差はありますがやることとしてはほぼ同じです。
ここで重要なのは必要以上の水分を摂取することです。一週間前ほどから非常に多くの水分を摂取し、大会当日に近づくにつれて水分の摂取量を減らしていきます。
必要以上の水分は体にダメージになりますが、体はそれを体外に排出していく機能があります。日本の気候を考えてもこれくらいになるかと思います。
特に最初の数日は摂った水分以上の水を排出しようとするため体は水を溜め込もうとしなくなります。
利尿作用のあるアスパラ、パインなどの果物やビタミンCやBを摂ることも有効です。
大会当日の土曜日は必要に応じて、のどが乾いたら飲む程度に摂取します。後述しますが木曜日からはカーボローディングと並行します。カーボローディングには水分も必要になります。
女性の場合
女性の場合は特に水分を摂りすぎることでのむくみを恐れている選手が多いように感じます。しかし必要以上に摂取することで体外へ排出されます。
下半身の血流に問題がある場合は適用されないことがありますが、日常的にトレーニングをしている方であれば問題ないかと思います。
私の推奨するプロトコルではビタミンと水を摂取しますが、ロシアの選手では利尿作用を目的としてウォッカを飲む事もあるようです。
下半身の血流に問題がある場合は適用されないことがありますが、日常的にトレーニングをしている方であれば問題ないかと思います。
私の推奨するプロトコルではビタミンと水を摂取しますが、ロシアの選手では利尿作用を目的としてウォッカを飲む事もあるようです。
塩とカーボに関して

理論上、米をたくさん食べれば体内のグリコーゲン量は増えます。そのためカーボローディングを行ったときに体重に変化がなければそれは正しく行えていません。カーボローディングを行っているつもりでも実際は行えていない事もあります。
それは塩分の摂取量に問題があるかもしれません。必要な量の塩分が摂れていないケースです。大会前には十分な塩分を摂取しておく必要があります。
長期間の減量で塩分が不足すると、細胞内にグルコースを運ぶ働きのSGLUTが作られず、体内にグルコースが増やせません。そのため、カーボを多く摂っても体内に溜まらず体重の変動も起きません。
選手の間で塩分が嫌われ、恐れられていることも知っています。しかし実際は真逆で、塩分は必要です。
大会数日前にいきなり導入することが不安であれば、期間に余裕がある段階で一度試してみることを推奨します。その時の変化の様子で本番前にどうするかを決めることもできます。実際に私自身もそうしました。
カーボローディングにしても体重が増えなければカーボローディングではなく、失敗です。そのときはカーボの量を増やさずに塩の摂取量を増やしてみてください。カーボを摂取しても体重が増えない人の6割ほどはこれで増やせました。
一方、残りの4割ほどは別の要因だと思います。大会への不安や緊張から神経質になりすぎたり、アドレナリンが出過ぎたりです。アドレナリンは筋からグリコーゲンを放出する作用があるので、アドレナリンが出ているとせっかくのカーボが出て行ってしまいます。
玄米は白米に比べてカーボロードの効果が緩やかになりますが、普段から玄米で減量を進めているのであれば玄米を用いて問題ありません。
カーボロードは減量中に食べていたものをそのまま用いるのが望ましく、わざわざ別の米を使う必要はありません。その方が体も慣れています。
それは塩分の摂取量に問題があるかもしれません。必要な量の塩分が摂れていないケースです。大会前には十分な塩分を摂取しておく必要があります。
長期間の減量で塩分が不足すると、細胞内にグルコースを運ぶ働きのSGLUTが作られず、体内にグルコースが増やせません。そのため、カーボを多く摂っても体内に溜まらず体重の変動も起きません。
選手の間で塩分が嫌われ、恐れられていることも知っています。しかし実際は真逆で、塩分は必要です。
大会数日前にいきなり導入することが不安であれば、期間に余裕がある段階で一度試してみることを推奨します。その時の変化の様子で本番前にどうするかを決めることもできます。実際に私自身もそうしました。
カーボローディングにしても体重が増えなければカーボローディングではなく、失敗です。そのときはカーボの量を増やさずに塩の摂取量を増やしてみてください。カーボを摂取しても体重が増えない人の6割ほどはこれで増やせました。
一方、残りの4割ほどは別の要因だと思います。大会への不安や緊張から神経質になりすぎたり、アドレナリンが出過ぎたりです。アドレナリンは筋からグリコーゲンを放出する作用があるので、アドレナリンが出ているとせっかくのカーボが出て行ってしまいます。
玄米は白米に比べてカーボロードの効果が緩やかになりますが、普段から玄米で減量を進めているのであれば玄米を用いて問題ありません。
カーボロードは減量中に食べていたものをそのまま用いるのが望ましく、わざわざ別の米を使う必要はありません。その方が体も慣れています。
ナトリウム/カリウムの摂取
少し古い方法で、生理学の基本的な授業で習うカリウム/ナトリウムポンプを踏まえた内容になります。この方法はカリウムとナトリウムが体内に十分にあればやらなくても良いプロトコルです。また、注意点として先ほどの塩を多く摂る方法とは両立できません。
人体の65%は水分です。100㎏の人であれば65㎏が水分。
そのうち2/3の43㎏は細胞内にあり、残る1/3は22㎏細胞外にあります。この細胞内外の水分量のバランスを調節しているのがカリウムとナトリウムです。
土曜が大会であれば月~水曜は塩分を多く摂取し、カリウムは摂取しない。
木曜と金曜には塩を一切摂取せず、その分カリウムの摂取量を増やします。
ナトリウムを制限することでむくみの原因となる細胞外の水分量を減らし、カリウムを多く摂取することで細胞内に水分を多く含むようにします。この点で先述の塩を多く摂取する方法と両立できません。
目安として、7~8回のポージング練習をして汗をかいていればこの手順の通りに進めて問題ありません。ポージング練習の後に汗をかいていなければこの方法は推奨しません。なお、この方法において水分量は変える必要はありません。
人体の65%は水分です。100㎏の人であれば65㎏が水分。
そのうち2/3の43㎏は細胞内にあり、残る1/3は22㎏細胞外にあります。この細胞内外の水分量のバランスを調節しているのがカリウムとナトリウムです。
土曜が大会であれば月~水曜は塩分を多く摂取し、カリウムは摂取しない。
木曜と金曜には塩を一切摂取せず、その分カリウムの摂取量を増やします。
ナトリウムを制限することでむくみの原因となる細胞外の水分量を減らし、カリウムを多く摂取することで細胞内に水分を多く含むようにします。この点で先述の塩を多く摂取する方法と両立できません。
目安として、7~8回のポージング練習をして汗をかいていればこの手順の通りに進めて問題ありません。ポージング練習の後に汗をかいていなければこの方法は推奨しません。なお、この方法において水分量は変える必要はありません。
最大限のグリコーゲン量を貯蔵するために
最大量のグリコーゲンを筋中に貯蔵した状態でステージに立つことが重要です。そのためには先に極度の疲労困憊の状態を経験する必要があります。
最終週のトレーニングは追い込まない強度での全身のウェイトトレーニングと有酸素、ポージング練習に留めること。
最終週のトレーニングは追い込まない強度での全身のウェイトトレーニングと有酸素、ポージング練習に留めること。
大会前日の食事に関して
大会前にはたくさん食べておくことが大事です。大会前日の夕食はカーボと脂質の多い食事となります。信じ難いかもしれませんが、私が指導している選手は皆そうしています。
大会後に、大会当日よりも良いコンディションだった経験はありませんか?言うまでもなく、どれだけ良いコンディションになったところで大会後では意味がありません。大会前にたくさん食べるのです。そのテストを2~3週間前に試してみてほしいです。
大会後に、大会当日よりも良いコンディションだった経験はありませんか?言うまでもなく、どれだけ良いコンディションになったところで大会後では意味がありません。大会前にたくさん食べるのです。そのテストを2~3週間前に試してみてほしいです。
大会当日
しっかりと8時間の睡眠をとり、前日までの仕上がったコンディションを保つことが目標です。当日は少しずつカーボを補充し続け、水分の摂取はなるべく抑えること。
それと並行して待機時間は寝そべり足を高くしておくことも重要です。
選手はステージ裏でよく寝転んでいますが、なぜそうしているかご存じでしょうか。体内の水分が重力で下へ落ちていく事を避けるためです。靴下を脱いだ時のことを思い出してください、むくんだ皮膚に跡が残っていると思います。
それと並行して待機時間は寝そべり足を高くしておくことも重要です。
選手はステージ裏でよく寝転んでいますが、なぜそうしているかご存じでしょうか。体内の水分が重力で下へ落ちていく事を避けるためです。靴下を脱いだ時のことを思い出してください、むくんだ皮膚に跡が残っていると思います。
最後に
これらのやり方はカテゴリによってというよりは選手個々の体型、体質、状態などによっても変わってくると思います。くれぐれもピークウィークでは追い込みすぎないように頑張ってください。