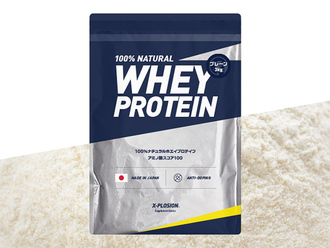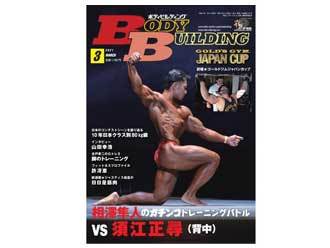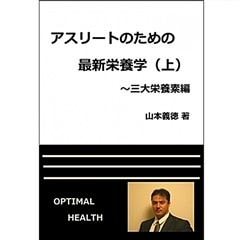カルシウムの摂取量は?
掲載日:2020.07.16
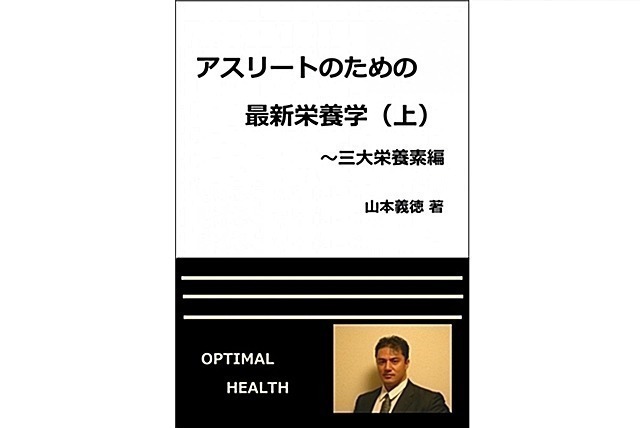
カルシウムの必要性については十分に分かったと思いますが、摂取量が多くてもダメだということはカルシウム・パラドックスの項で説明しました。
実際のところ、一日にどれくらいのカルシウムを摂れば良いのでしょうか。
平成25年の国民健康・栄養調査の結果では、男性は平均520mg、女性は平均489mgが一日の摂取量となっています。しかし厚生労働省の推奨摂取量は男性の場合、12~14歳で1000mg、15~29歳は800mg、30~49歳でも650mg。女性の場合は12~14歳で800mg、15歳以上は650mgが推奨摂取量となります。
つまり現状では「食事からのカルシウム摂取だけでは不足している」ということになります。カルシウム摂取量が増加する(一日300mg)と、大腸がんのリスクが低下したという報告があります。(※22)しかし前立腺がんのリスクは増えたという報告もあります。(※23)
また肥満成人154名に350mgのカルシウムとビタミンD100IUが入ったオレンジジュースを一日3回飲ませて16週間経過したところ、内臓脂肪が減少したという報告があります。(※24)
さらに肥満者を対象とした低カルシウム摂取群(一日400~500mg)と高カルシウム摂取群(一日1100mg)を比較したところ、高カルシウム摂取群では体重減少と中心性肥満の改善が認められたとされています。(※25)
カルシウム摂取で体脂肪が減少する機序は良く分かっていないのですが、カルシウムが足りないと細胞外の活性型ビタミンDが増えて細胞内へのカルシウム流入が増加し、脂肪酸脂肪酸合成が促進されると言われています。(※26)
また疫学調査ではカルシウム摂取不足によるパラソルモン上昇は血圧やウェストサイズ、インスリン抵抗性の増加や糖尿病発症リスク上昇、HDLコレステロールの減少と関連しているようです。(※27,※28)
なおカルシウム・パラドックスの項で「カルシウム単独摂取だと骨折は減らない」と書きましたが、同時にビタミンDをサプリメントとして補給すると効果はあるようです。一日に1200mgのカルシウムと800IUのビタミンDが推奨されています。(※29,※30)
厚生労働省の定める「耐容上限量」は一日2500mgです。そしてここまでの研究から考えて、一日のカルシウム摂取量は1000mg前後が適切な摂取量だと思われます。
前述の通り、食事からの摂取は男性で平均520mg、女性は平均489mgだということを考えると、サプリメントとして一日に200~300mg程度を補うとともに、ビタミンDを一日に1000~2000IU摂取することを筆者としては勧めたいと思います。なおカルシウムはマグネシウムとのバランスが重要ですので、マグネシウムも併せて摂取するべきです。詳しくはマグネシウムの項をお読みください。
カルシウムは乳製品や小魚、海藻類、切り干し大根、凍り豆腐などに多く含まれます。また玄米などに多く含まれるフィチン酸や、ホウレンソウなどに多く含まれるシュウ酸はカルシウムの吸収を妨げるため、食べ過ぎは禁物です。
また、牛乳が材料なので当然ですが、ホエイプロテインにもにもカルシウムが含まれます。
製造方法によって異なりますが、だいたいホエイプロテイン100gあたり、カルシウムは250~400mgくらい含まれていますので、プロテインを大量に飲む人はカルシウムをサプリメンテーションする必要はないかもしれません。サプリメントとしてはクエン酸カルシウムや酢酸カルシウムは吸収されやすく、炭酸カルシウムは吸収されにくいことが分かっています。
実際のところ、一日にどれくらいのカルシウムを摂れば良いのでしょうか。
平成25年の国民健康・栄養調査の結果では、男性は平均520mg、女性は平均489mgが一日の摂取量となっています。しかし厚生労働省の推奨摂取量は男性の場合、12~14歳で1000mg、15~29歳は800mg、30~49歳でも650mg。女性の場合は12~14歳で800mg、15歳以上は650mgが推奨摂取量となります。
つまり現状では「食事からのカルシウム摂取だけでは不足している」ということになります。カルシウム摂取量が増加する(一日300mg)と、大腸がんのリスクが低下したという報告があります。(※22)しかし前立腺がんのリスクは増えたという報告もあります。(※23)
また肥満成人154名に350mgのカルシウムとビタミンD100IUが入ったオレンジジュースを一日3回飲ませて16週間経過したところ、内臓脂肪が減少したという報告があります。(※24)
さらに肥満者を対象とした低カルシウム摂取群(一日400~500mg)と高カルシウム摂取群(一日1100mg)を比較したところ、高カルシウム摂取群では体重減少と中心性肥満の改善が認められたとされています。(※25)
カルシウム摂取で体脂肪が減少する機序は良く分かっていないのですが、カルシウムが足りないと細胞外の活性型ビタミンDが増えて細胞内へのカルシウム流入が増加し、脂肪酸脂肪酸合成が促進されると言われています。(※26)
また疫学調査ではカルシウム摂取不足によるパラソルモン上昇は血圧やウェストサイズ、インスリン抵抗性の増加や糖尿病発症リスク上昇、HDLコレステロールの減少と関連しているようです。(※27,※28)
なおカルシウム・パラドックスの項で「カルシウム単独摂取だと骨折は減らない」と書きましたが、同時にビタミンDをサプリメントとして補給すると効果はあるようです。一日に1200mgのカルシウムと800IUのビタミンDが推奨されています。(※29,※30)
厚生労働省の定める「耐容上限量」は一日2500mgです。そしてここまでの研究から考えて、一日のカルシウム摂取量は1000mg前後が適切な摂取量だと思われます。
前述の通り、食事からの摂取は男性で平均520mg、女性は平均489mgだということを考えると、サプリメントとして一日に200~300mg程度を補うとともに、ビタミンDを一日に1000~2000IU摂取することを筆者としては勧めたいと思います。なおカルシウムはマグネシウムとのバランスが重要ですので、マグネシウムも併せて摂取するべきです。詳しくはマグネシウムの項をお読みください。
カルシウムは乳製品や小魚、海藻類、切り干し大根、凍り豆腐などに多く含まれます。また玄米などに多く含まれるフィチン酸や、ホウレンソウなどに多く含まれるシュウ酸はカルシウムの吸収を妨げるため、食べ過ぎは禁物です。
また、牛乳が材料なので当然ですが、ホエイプロテインにもにもカルシウムが含まれます。
製造方法によって異なりますが、だいたいホエイプロテイン100gあたり、カルシウムは250~400mgくらい含まれていますので、プロテインを大量に飲む人はカルシウムをサプリメンテーションする必要はないかもしれません。サプリメントとしてはクエン酸カルシウムや酢酸カルシウムは吸収されやすく、炭酸カルシウムは吸収されにくいことが分かっています。
[ アスリートのための最新栄養学(上) ]