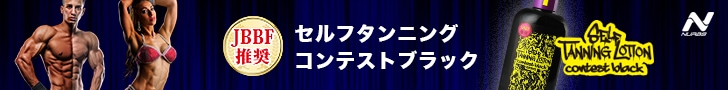ボディビル風雲録 ①
月刊ボディビルディング1969年1月号
掲載日:2017.12.05
田鶴浜 弘
人間は忘れっぼいものである。みんなが、いやーーというほど、身体で味わわされたはずの、まだ20年ほどしかたっていない終戦の頃の、みじめな記憶はもうスッカリうすれてしまっただろう。
満洲から捕虜ボケして帰って来た僕が、敗戦の荒廃した東京の街に立ったのは昭和21年10月だった。
見渡すかぎり焼土と焼けビル、それに。バラックばかりだった。
そして、敗残が、日本人を4等国民におちぶれさせている。
おびただしいクタビレて、うす汚れた貧相な東京市民は、空きっ腹--芋づるの味噌汁だの、ドングリ粉まで食った。
兵隊服の“特攻くずれ”が看板のヤミ米運搬屋だけが、たくましく見えた。
芋アメが貴重品で、モンサントのサッカリンで儲けた奴が、メチールアルコールに呑んだくれて失明したりお陀仏になった。
イキのいい進駐軍の天下で、彼等だけがパリッとして見え灯がともる頃になると、パン助どもが、兵隊に群がった。
いや、まだいるーー銀シャリを食わせる第三国人の店がにぎわった。
少なくとも当時の彼等は日本人よりも一枚格が高い優秀民族であった。
“日本は、一体、何時になったら立ち直れるのかしら?”
日本民族のエネルギーは、どう見たって今や消えかけている。
それに、進駐軍の兵隊たちの肉体からして逞ましいだけに、東京中の焼けビルやバラックにひしめいている俺達の仲間が、ひどくはかなく見えるのだ。
民族のエナージーのボルテージが、今やまるで違ってしまったーーというコンプレックス感にとりつかれてしまう。
虚脱した敗戦の環境の中で、ヒシヒシと、日本民族のあわれさを感じると同時に、
“太陽を日本人の肉体の中で燃えさせなくてはいけない”という、まことに奇妙な文句がひらめくのである。
こうした東京の街を背景にしていない今、この文句は実感を伴わないだろう。
36階の摩天楼から大東京を俯瞰し、立体交差のハイウエイが自動車の血管になってしまい、穴倉の深夜バーでサイケ調のふうてんどもがビートのリズムでロレッている現代のムードではたしかにピンと来ない。
だが、そのときの僕の思念はこうだった。
つい先だってまでの回想ーー凍結した北満の灰色の捕虜生活の断片がありありと心底によみがえった。
その中からのひらめきーーエナージーが、いや肉体が、場合によっては筋肉が、スピリットを、そして思想も、教養も、学も、さては文明を文化を生み出し、支えているのだーーと、それこそ、全身全霊で痛いほど思い知らされたーーその回想の具体的な幾つかのことがアリアリと浮かぶのである。
*
北満の長白山系に連らなる中腹、眼下の豆満江沿いの対岸が北鮮の会寧の港ーーという岩山で終戦を迎え、北鮮の延吉の捕虜収容所で、零下30度のきびしい越冬をした。
捕虜収容所の宿舎は昔の馬小屋であった。
昼夜ソ連兵に機銃で監視されながらの使役ーー旧関東軍糧秣の運搬、旧関東軍施設の取りこわし作業で、目ぼしいものは、貨車積みしてソ連に持ち去るのである。
給与は、飯盒のフタに盛り切りのうすい高梁がゆか、トーモロコシや大豆だけーー激しい使役作業の連続、おまけに四六時中着たきり雀だから、全身はしらみの巣で、身体を掻いたハダからは壊血病のドス黒い血が噴き出し、栄養失調症状の下痢になやまされた。冬になる頃には、少くとも収容人員の1/3は死亡した。
この極端な欠乏の中でも、人間というものは環境に順応した生活の知慧が生きるために役立つ積極的な建設の努力が、何かしら、それなりの文化(?)を生み出し、手段を発見して行くものである。
捕虜の殆どは、赤紙で応召した補充兵と、若干の在留日本人だから、彼等の中には、大学教授や、政府の高官ーーつまり教養とか学識の高いものも居た。
だが、こうした生活の中で生きるための知慧がひらめくのは身につけた教養とか学識の高さに無関係で、知能は実に肉体のコンディションと平行して働らくものだという事を知った。
社会生活が恵まれていたが為に、欠乏の生活に耐えられなかった者もあるだろうが、必ずしも高級な生活環境から捕虜生活に入って欠乏の生活に敗れるとは限らない。
“人間の身体は発電所みたいなものだネ、知識も勇気も意欲も、みんな身体から湧くエナージーの産物なんだヨ、だから究極の人間の働らきに脳ミソなんか、ほんの一部分にすぎん”
捕虜生活で一番親しくしていた学究に似ず頑健な肉体の新京大学の哲学教授が何時もこういった。
*
不屈の闘志ーーとか気魄などというものも肉体のエナージーに支えられているのだということを、その頃に身を以って思い知ったのである。
捕虜収容所における灰色の月日が流れるにつれて、馬小屋の中から、毎晩のように誰かしら消えていった。
“人が死ぬ”という厳粛な感じではなくて、焔がもえ尽きるような、“消えるーー”という表現が一番ぴったりするのだ。
同じように空腹をかかえ、使役で激しいエナージーの消耗ーーだが、生き残る奴と、虫けらのように消えてゆくアワレな奴の運命の別れ目は、生き残るための知慧の働らきーーそのホンの僅かのちがいからであった。
その哀れな、はかない奴等には、いづれも共通の前徴があらわれる。
消える前には揃いも揃って知能の働らきが、そしてあらゆる意欲がなくなってしまうのである。
“可哀そうにーーあんな頭のいい奴だったのにボケて来やがってーーもうおしまいだヨ”
頑健な肉体の哲学教授が私にそういったのは、高い教養を持っているはずの、元は満洲国政府の高官だった男で、それが無教養のはずの連中よりも知慧の程度がまるっきり低くなってしまった。
こうした環境で、いやというほど思い知らされるのは、知能も意欲も、所詮は肉体のエナージーに比例するーーという事実であった。
健全な肉体に健全な精神が宿るーーという平凡な真理が、ここでは毎日、目の前に躍如としていた。
ギリギリの生と死を賭けて、嘘もいつわりも通用しない。
*
大東京のど真ン中に焼ケ野原がまだ残っていて、四等国民の1人に成り下った自嘲が、ここはまだ延吉の捕虜収容所の延長のような気がしたりする。
バイタリティとエナージーが何よりもの憧れであった。
太陽が欲しかったのであるーー八重州通り大阪商船ビルの一角に僕は事務所を設け(というよりこのビルの空いているスペースに坐り込んだというのが適切であった)“太陽興業株式会社”の看板をあげた。
“ボディビル風雲録”の本筋に入ってから、のちにその事務所から私が本筋に登場することになるのだが、そのときの私の心底には、延吉の馬小屋の中で、新京大学の哲学教授だった捕虜仲間の詞がやけついているのである。
満洲から捕虜ボケして帰って来た僕が、敗戦の荒廃した東京の街に立ったのは昭和21年10月だった。
見渡すかぎり焼土と焼けビル、それに。バラックばかりだった。
そして、敗残が、日本人を4等国民におちぶれさせている。
おびただしいクタビレて、うす汚れた貧相な東京市民は、空きっ腹--芋づるの味噌汁だの、ドングリ粉まで食った。
兵隊服の“特攻くずれ”が看板のヤミ米運搬屋だけが、たくましく見えた。
芋アメが貴重品で、モンサントのサッカリンで儲けた奴が、メチールアルコールに呑んだくれて失明したりお陀仏になった。
イキのいい進駐軍の天下で、彼等だけがパリッとして見え灯がともる頃になると、パン助どもが、兵隊に群がった。
いや、まだいるーー銀シャリを食わせる第三国人の店がにぎわった。
少なくとも当時の彼等は日本人よりも一枚格が高い優秀民族であった。
“日本は、一体、何時になったら立ち直れるのかしら?”
日本民族のエネルギーは、どう見たって今や消えかけている。
それに、進駐軍の兵隊たちの肉体からして逞ましいだけに、東京中の焼けビルやバラックにひしめいている俺達の仲間が、ひどくはかなく見えるのだ。
民族のエナージーのボルテージが、今やまるで違ってしまったーーというコンプレックス感にとりつかれてしまう。
虚脱した敗戦の環境の中で、ヒシヒシと、日本民族のあわれさを感じると同時に、
“太陽を日本人の肉体の中で燃えさせなくてはいけない”という、まことに奇妙な文句がひらめくのである。
こうした東京の街を背景にしていない今、この文句は実感を伴わないだろう。
36階の摩天楼から大東京を俯瞰し、立体交差のハイウエイが自動車の血管になってしまい、穴倉の深夜バーでサイケ調のふうてんどもがビートのリズムでロレッている現代のムードではたしかにピンと来ない。
だが、そのときの僕の思念はこうだった。
つい先だってまでの回想ーー凍結した北満の灰色の捕虜生活の断片がありありと心底によみがえった。
その中からのひらめきーーエナージーが、いや肉体が、場合によっては筋肉が、スピリットを、そして思想も、教養も、学も、さては文明を文化を生み出し、支えているのだーーと、それこそ、全身全霊で痛いほど思い知らされたーーその回想の具体的な幾つかのことがアリアリと浮かぶのである。
*
北満の長白山系に連らなる中腹、眼下の豆満江沿いの対岸が北鮮の会寧の港ーーという岩山で終戦を迎え、北鮮の延吉の捕虜収容所で、零下30度のきびしい越冬をした。
捕虜収容所の宿舎は昔の馬小屋であった。
昼夜ソ連兵に機銃で監視されながらの使役ーー旧関東軍糧秣の運搬、旧関東軍施設の取りこわし作業で、目ぼしいものは、貨車積みしてソ連に持ち去るのである。
給与は、飯盒のフタに盛り切りのうすい高梁がゆか、トーモロコシや大豆だけーー激しい使役作業の連続、おまけに四六時中着たきり雀だから、全身はしらみの巣で、身体を掻いたハダからは壊血病のドス黒い血が噴き出し、栄養失調症状の下痢になやまされた。冬になる頃には、少くとも収容人員の1/3は死亡した。
この極端な欠乏の中でも、人間というものは環境に順応した生活の知慧が生きるために役立つ積極的な建設の努力が、何かしら、それなりの文化(?)を生み出し、手段を発見して行くものである。
捕虜の殆どは、赤紙で応召した補充兵と、若干の在留日本人だから、彼等の中には、大学教授や、政府の高官ーーつまり教養とか学識の高いものも居た。
だが、こうした生活の中で生きるための知慧がひらめくのは身につけた教養とか学識の高さに無関係で、知能は実に肉体のコンディションと平行して働らくものだという事を知った。
社会生活が恵まれていたが為に、欠乏の生活に耐えられなかった者もあるだろうが、必ずしも高級な生活環境から捕虜生活に入って欠乏の生活に敗れるとは限らない。
“人間の身体は発電所みたいなものだネ、知識も勇気も意欲も、みんな身体から湧くエナージーの産物なんだヨ、だから究極の人間の働らきに脳ミソなんか、ほんの一部分にすぎん”
捕虜生活で一番親しくしていた学究に似ず頑健な肉体の新京大学の哲学教授が何時もこういった。
*
不屈の闘志ーーとか気魄などというものも肉体のエナージーに支えられているのだということを、その頃に身を以って思い知ったのである。
捕虜収容所における灰色の月日が流れるにつれて、馬小屋の中から、毎晩のように誰かしら消えていった。
“人が死ぬ”という厳粛な感じではなくて、焔がもえ尽きるような、“消えるーー”という表現が一番ぴったりするのだ。
同じように空腹をかかえ、使役で激しいエナージーの消耗ーーだが、生き残る奴と、虫けらのように消えてゆくアワレな奴の運命の別れ目は、生き残るための知慧の働らきーーそのホンの僅かのちがいからであった。
その哀れな、はかない奴等には、いづれも共通の前徴があらわれる。
消える前には揃いも揃って知能の働らきが、そしてあらゆる意欲がなくなってしまうのである。
“可哀そうにーーあんな頭のいい奴だったのにボケて来やがってーーもうおしまいだヨ”
頑健な肉体の哲学教授が私にそういったのは、高い教養を持っているはずの、元は満洲国政府の高官だった男で、それが無教養のはずの連中よりも知慧の程度がまるっきり低くなってしまった。
こうした環境で、いやというほど思い知らされるのは、知能も意欲も、所詮は肉体のエナージーに比例するーーという事実であった。
健全な肉体に健全な精神が宿るーーという平凡な真理が、ここでは毎日、目の前に躍如としていた。
ギリギリの生と死を賭けて、嘘もいつわりも通用しない。
*
大東京のど真ン中に焼ケ野原がまだ残っていて、四等国民の1人に成り下った自嘲が、ここはまだ延吉の捕虜収容所の延長のような気がしたりする。
バイタリティとエナージーが何よりもの憧れであった。
太陽が欲しかったのであるーー八重州通り大阪商船ビルの一角に僕は事務所を設け(というよりこのビルの空いているスペースに坐り込んだというのが適切であった)“太陽興業株式会社”の看板をあげた。
“ボディビル風雲録”の本筋に入ってから、のちにその事務所から私が本筋に登場することになるのだが、そのときの私の心底には、延吉の馬小屋の中で、新京大学の哲学教授だった捕虜仲間の詞がやけついているのである。
月刊ボディビルディング1969年1月号
Recommend
-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!
- BESTBODY JAPAN
- BESTBODY JAPAN Vol.2
- 金額: 1,527 円(税込)
-