バーベル放談⑫
友情の〝一発〟
月刊ボディビルディング1969年7月号
掲載日:2018.02.26
アサヒ太郎
青くさい説教調の話が続いて申訳ない。
ここらで、ちょっぴりニヤリとする〝世界こぼれ話〟に切り換えよう。
バーベルを持つ手をしばらく休めて、バカ笑いしていただきたい。
ここらで、ちょっぴりニヤリとする〝世界こぼれ話〟に切り換えよう。
バーベルを持つ手をしばらく休めて、バカ笑いしていただきたい。
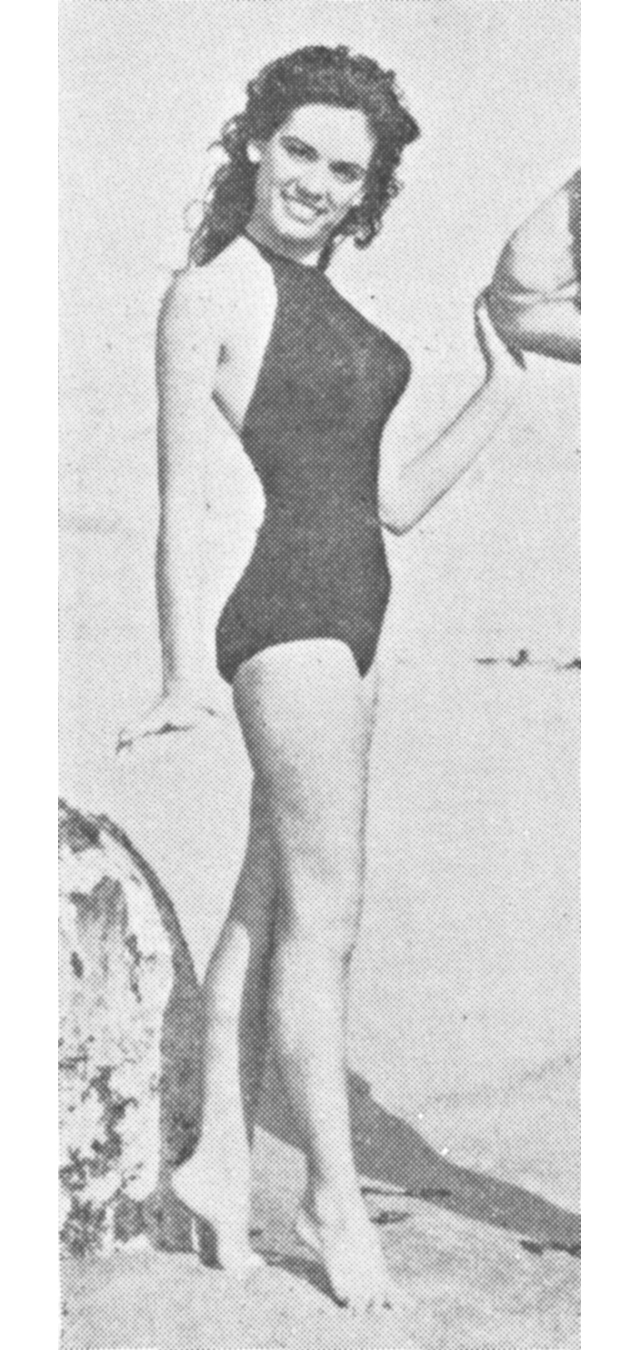
海岸であった美女エンジェル
<友情に国境なし>
私の先輩がロンドンに駐在中、スージーという女の子とねんごろになった。女の子、といっても、もちろん20歳をいくつか出ている娘であることをお断わりしておく。
スージーは、教養も、知性もなく、飛切り美人というわけでもない。ただ田舎から志を抱いてロンドンにやってきたというむちむちした可愛いグラマー娘である。
先輩が、この〝むちむち娘〟と割りない仲になったのは、歴代駐在員の〝引継ぎガール〟だからである。先輩の先輩、そしてまた先輩の先輩の先輩も、この娘をかわいがって来た関係で
AからB、BからCと、つぎつぎバトンタッチされるというわけである。
さて、スージーは、こんな商売をしている女なので、とくに決った下宿を持たない。が、日本のジェントルメンにごひいきになっているので、別段食う心配はない。時折り、電話連絡で契約をかわすと、ふらりとやってきて用件をすませる。契約料はいくらか聞き忘れたが、たぶん10ポンドか、その前後だったと思う。
先輩は、こうして時折りスージーと逢う瀬を楽しんでいたが、ある日パリの会議に出席するよう本社から訓電を受けた。そこで、しばらくロンドンを留守にするからとの理由でスージーと連絡、当分の別れを惜しんだ。
その夜、スージーがしみじみ語ったもちろん英語で。先輩は、そのころまだたいしてうまい英語使いとも思えなかったが、こういう話は以心伝心、大体わかるものなのである。
スージー「わたし、こんな生活をいつまでも続けてはダメだと思うの」
先輩「その通りだ。スージー。一日も早くこんな商売から足を洗って、まともな仕事についた方がいいね」
スージー「本当に私もそう思うわ。どんな仕事がいいかしら」
先輩「電話交換手なんかどうだろう。講習会を受けて資格を取ったらどうたい」
スージー「そうね、考えてみるわ」
まあ、ざっとこんな調子のやりとりがあったようだ。
翌日は日曜だった。スージーは先輩の言葉を聞いて、ともかく落着く先を探し、それから今後の身の振り方を考えることになった。
スージーの更生のためなら、と先輩は出発の前の多忙な時間を割き、車でスージーの下宿先をいっしょに探し回った。
ウエストミンスター寺院の鐘が、静かなロンドン市内に鳴りひびくのを聞きながら、先輩は下宿街を徐行した。
一軒、一軒、スージーは戸をたたいて部屋が空いているかどうかを確かめているようだが、明らかに商売女とわかるスージーの様子に、どの下宿屋も冷淡に手を振って断わっているようだ。.
スージーが戻ってくる。ダメだったと手を振る。先輩は、さらに車を数メートル先きに進める。スージーが戸をたたく。ダメ。悲しそうな表情だ。また一軒、こんどもダメ。さらにもう一軒、それも断わられた。スージーの顔がゆがみ、いまにも泣出しそうだ。
先輩の顔もゆがんだ。ウエストミンスター寺院のビッグ・ベンがやけに悲しそうにひびく。パントマイムのようなシーンがしばらく続いたが、とうとうスージーは一軒の下宿先も見つけることができなかった。プーア・スージー(可哀そうなスージー)
先輩は、余り男前でない顔をしかめて心で泣いた。なんとかしてやらねば
ともに体を触れ合った仲ほど深いものはない。まして、お互いにいたわり慕い合う仲だ。
先輩は決心した。よし、今晩はオレのアパートに泊めよう。どうせ出発は明日だ。今晩ひと晩ぐらい泊めてやらなければ、これまでの恩義にむくいるチャンスはない
先輩は、やさしくスージーに呼びかけた(と私は信じている)
先輩「スージー、おいで。もうあきらめよう」
スージー「わたしってダメね。(どこかテレビで聞いたようなセリフだが……)だれも相手にしてくれないわ」
先輩「いいよ、いいよ。今晩はオレのアパートに来てゆっくり寝なさい」
スージー「でも、ご迷惑じゃないかしら」
先輩「大丈夫だ。オレの出発は明日なんだから……」
スージー「それじゃ、お言葉に甘えて泊めていただこうかしら」
このときも、多分こんな会話がかわされたと私は確信する。
かくて、2人はふたび元の道を引返した。
先輩は、その夜会議出席の準備で忙しかった。ヒゲそり、パンツ2枚、アンダーシャツ3枚、カッターシャツ3枚、えーとクツ下は、花のパリで買うとするか
まあ、こんな具合いでスーツケースを準備した。
その間、スージーは別室のベッドで体を横たえ、じっと何か考え込んでいる様子だった。
準備を終え、お休みを言おうと先輩は部屋をのぞいた。
すると、スージーはゆたかな胸もあらわに、先輩を見てにっこり笑った。
むらむらっときた。男のあさましさ
先輩は、その盛りあがった真っ白いバストをみたとたん、あすの出発を忘れた。
熱いベーゼ(多分、またまた多分で申訳ないが、事の運びは、こんな具合いになるはずだ)そして……。
2人の体がやがて分れたとき、紅潮したスージーの口から、先輩にとってはいまだに忘れることのできない言葉が洩れた。
「This is one-shot of friendship.」
<おカネは要らないのよ。これは私の友情の〝1発〟よ>
感激! 先輩は、スージーのかれんな気持を思って、男泣きに(これはちょっとオーバー)泣いた。
翌月曜日、先輩はパリに向って出発した。
スージーは、空港でさびしそうに手を振っていた。<さよなら、さよなら、さよなら>
(これも、どこかで聞いたような言葉だが……)
約1週間の仕事をすませ、先輩はロンドンに戻ってきた。
「あのスージーは、どこへ行ったろう
先輩は、ひまあるたびにロンドンの町なかを探し歩いた。もちろん、夜である。しかし、スージーの姿は、2度と見ることがなかった。
ついでに、申上げておくが、ハイドパークに咲くロンドンの〝夜の花〟の情人は、ほとんどが黒人である。
何故か?黒人の体は、ボディビルダーのようにたくましいからである。
30を越えると、またたく間に老けて行く白人の男女にくらべ、黒人男女のハダはつやつやと光り、すばらしい弾力性に富んでいる。
白人は、奴れいを酷使して、体を使う事を忘れたが、黒人は馬車馬のごとく働らき、その貴重な生物学的な遺産を子孫に伝えた。
自動車に乗り、歩く事を忘れた白人
牛の如く歩み、馬のように働らき続けた黒人。百数十年の歴史は、ついに白人の女をして黒人になびかせてしまった、という見解は間違っているだろうか。
あの有名なノーベル賞候補作家、三島由紀夫先生はいっているではないか
詩人の顔と、そして闘牛士の体。
スージーは、教養も、知性もなく、飛切り美人というわけでもない。ただ田舎から志を抱いてロンドンにやってきたというむちむちした可愛いグラマー娘である。
先輩が、この〝むちむち娘〟と割りない仲になったのは、歴代駐在員の〝引継ぎガール〟だからである。先輩の先輩、そしてまた先輩の先輩の先輩も、この娘をかわいがって来た関係で
AからB、BからCと、つぎつぎバトンタッチされるというわけである。
さて、スージーは、こんな商売をしている女なので、とくに決った下宿を持たない。が、日本のジェントルメンにごひいきになっているので、別段食う心配はない。時折り、電話連絡で契約をかわすと、ふらりとやってきて用件をすませる。契約料はいくらか聞き忘れたが、たぶん10ポンドか、その前後だったと思う。
先輩は、こうして時折りスージーと逢う瀬を楽しんでいたが、ある日パリの会議に出席するよう本社から訓電を受けた。そこで、しばらくロンドンを留守にするからとの理由でスージーと連絡、当分の別れを惜しんだ。
その夜、スージーがしみじみ語ったもちろん英語で。先輩は、そのころまだたいしてうまい英語使いとも思えなかったが、こういう話は以心伝心、大体わかるものなのである。
スージー「わたし、こんな生活をいつまでも続けてはダメだと思うの」
先輩「その通りだ。スージー。一日も早くこんな商売から足を洗って、まともな仕事についた方がいいね」
スージー「本当に私もそう思うわ。どんな仕事がいいかしら」
先輩「電話交換手なんかどうだろう。講習会を受けて資格を取ったらどうたい」
スージー「そうね、考えてみるわ」
まあ、ざっとこんな調子のやりとりがあったようだ。
翌日は日曜だった。スージーは先輩の言葉を聞いて、ともかく落着く先を探し、それから今後の身の振り方を考えることになった。
スージーの更生のためなら、と先輩は出発の前の多忙な時間を割き、車でスージーの下宿先をいっしょに探し回った。
ウエストミンスター寺院の鐘が、静かなロンドン市内に鳴りひびくのを聞きながら、先輩は下宿街を徐行した。
一軒、一軒、スージーは戸をたたいて部屋が空いているかどうかを確かめているようだが、明らかに商売女とわかるスージーの様子に、どの下宿屋も冷淡に手を振って断わっているようだ。.
スージーが戻ってくる。ダメだったと手を振る。先輩は、さらに車を数メートル先きに進める。スージーが戸をたたく。ダメ。悲しそうな表情だ。また一軒、こんどもダメ。さらにもう一軒、それも断わられた。スージーの顔がゆがみ、いまにも泣出しそうだ。
先輩の顔もゆがんだ。ウエストミンスター寺院のビッグ・ベンがやけに悲しそうにひびく。パントマイムのようなシーンがしばらく続いたが、とうとうスージーは一軒の下宿先も見つけることができなかった。プーア・スージー(可哀そうなスージー)
先輩は、余り男前でない顔をしかめて心で泣いた。なんとかしてやらねば
ともに体を触れ合った仲ほど深いものはない。まして、お互いにいたわり慕い合う仲だ。
先輩は決心した。よし、今晩はオレのアパートに泊めよう。どうせ出発は明日だ。今晩ひと晩ぐらい泊めてやらなければ、これまでの恩義にむくいるチャンスはない
先輩は、やさしくスージーに呼びかけた(と私は信じている)
先輩「スージー、おいで。もうあきらめよう」
スージー「わたしってダメね。(どこかテレビで聞いたようなセリフだが……)だれも相手にしてくれないわ」
先輩「いいよ、いいよ。今晩はオレのアパートに来てゆっくり寝なさい」
スージー「でも、ご迷惑じゃないかしら」
先輩「大丈夫だ。オレの出発は明日なんだから……」
スージー「それじゃ、お言葉に甘えて泊めていただこうかしら」
このときも、多分こんな会話がかわされたと私は確信する。
かくて、2人はふたび元の道を引返した。
先輩は、その夜会議出席の準備で忙しかった。ヒゲそり、パンツ2枚、アンダーシャツ3枚、カッターシャツ3枚、えーとクツ下は、花のパリで買うとするか
まあ、こんな具合いでスーツケースを準備した。
その間、スージーは別室のベッドで体を横たえ、じっと何か考え込んでいる様子だった。
準備を終え、お休みを言おうと先輩は部屋をのぞいた。
すると、スージーはゆたかな胸もあらわに、先輩を見てにっこり笑った。
むらむらっときた。男のあさましさ
先輩は、その盛りあがった真っ白いバストをみたとたん、あすの出発を忘れた。
熱いベーゼ(多分、またまた多分で申訳ないが、事の運びは、こんな具合いになるはずだ)そして……。
2人の体がやがて分れたとき、紅潮したスージーの口から、先輩にとってはいまだに忘れることのできない言葉が洩れた。
「This is one-shot of friendship.」
<おカネは要らないのよ。これは私の友情の〝1発〟よ>
感激! 先輩は、スージーのかれんな気持を思って、男泣きに(これはちょっとオーバー)泣いた。
翌月曜日、先輩はパリに向って出発した。
スージーは、空港でさびしそうに手を振っていた。<さよなら、さよなら、さよなら>
(これも、どこかで聞いたような言葉だが……)
約1週間の仕事をすませ、先輩はロンドンに戻ってきた。
「あのスージーは、どこへ行ったろう
先輩は、ひまあるたびにロンドンの町なかを探し歩いた。もちろん、夜である。しかし、スージーの姿は、2度と見ることがなかった。
ついでに、申上げておくが、ハイドパークに咲くロンドンの〝夜の花〟の情人は、ほとんどが黒人である。
何故か?黒人の体は、ボディビルダーのようにたくましいからである。
30を越えると、またたく間に老けて行く白人の男女にくらべ、黒人男女のハダはつやつやと光り、すばらしい弾力性に富んでいる。
白人は、奴れいを酷使して、体を使う事を忘れたが、黒人は馬車馬のごとく働らき、その貴重な生物学的な遺産を子孫に伝えた。
自動車に乗り、歩く事を忘れた白人
牛の如く歩み、馬のように働らき続けた黒人。百数十年の歴史は、ついに白人の女をして黒人になびかせてしまった、という見解は間違っているだろうか。
あの有名なノーベル賞候補作家、三島由紀夫先生はいっているではないか
詩人の顔と、そして闘牛士の体。

ボリューム感あふれるサンディ
<マダム・バタフライ>
これは、先輩の話ではない。私自身のエピソードである。
カンボジアの首都、プノンぺン市内にはざっと600のシクロ(三輪タクシー)がある。
その運転手(といっても、自分で一生けんめいペダルを踏むドライバーだが…)の人に、孫という中国系カンボジア人がいた。
孫は、私の顔を見ると、どこまでも遠慮深げについて回った。私もつい情に負けて、毎日孫のシクロを専用に使うことになった。
ある晩、国際電信電報局へ出かけた帰り、孫がしきりにある女の所に寄ってくれと頼んだ。
「マスター、その女、かわいそう。ジャポンのキャプテン(船長さん)帰ってくるいって帰ってこない。女、かわいそう。
マスター、1度見る。よいか
カタコトの日本語と英語をごっちゃまぜにして、孫はこんな風に私をくどく。
前にのべたように、私は情にもろい。
やむを得ず、孫のいうままに、女のアパートを訪れた。
ご存じのように、カンボジアは元フランスの植民地。アパートはウナギの寝床のように長く、奥行が深い。
案内された女の部屋に着くまで、左右に3つ、4つ部屋がある。そのとき左の部屋の1つから赤ん坊の泣き声が聞えた。
私は、ハッと胸をつかれた。女は子供を抱えているのか。そのとたん、日本に残してきた娘の顔がちらと胸に浮んだ。
「マスター、マスター」孫の呼び声。
私は粗末な部屋の中央に、白っぼいアオザイ(両ワキの切れた中国風のドレス)を着た小さな女を見た。25。6歳か
両手を合わせ、静かな物腰で頭をさげる。
私も同じように手を合わせ、挨拶を返す。
小乗仏教の国カンボジアでは、こんな風に挨拶をするのだ。
孫が、ポン引よろしく私を誘う。
「マスター、この女かわいそう。おカネない。キャプテン、ノーカムバックウソついた。女、悲しいよ」
よくよく聞くと、まさに現代版お蝶夫人だ。
プノンペン市内にあるフランス系病院に勤める女は、月にわずか700リエールの給料をもらっているが、これではいかに物価が安いカンボジアでも苦しい1ドル(360円)は、公定ルートで35リエール、ヤミ値になると60リエールぐらいになる。つまり月給は4,000円足らずなのだ。
そこで、たまたまプノンペンの港に入ってきた日本の貨物船の船長が、現地妻としてこの女を囲った。やさしい船長さんだったようで、女は楽しい数週間を送った。船出の日がやってきたキャプテンはいった。
「かならず帰ってくるから、待っていてくれ」
女は、だまってジャポンの船長さんを見送った。
それから1年、キャプテンを待ちわびる女のせつない気持は、深まるばかりだが、いとしの君は、一向にやってこない。
かわって現れたのが、孫に連れられた私というわけだ。
うらさびしい表情。痛々しい様子。
私は胸がつまった。それでなくてもさっきの赤ん坊の泣き声で、私は聖僧のような境地である。
孫を通じて、私はこう伝えた。
「あなたの苦しい状態はよくわかります。しかし、私はいまおカネであなたと取引するような気持にはとてもなれない。このまま帰ります。許してください」
女は、悲しそうに目を伏せ、ふたたび合掌して静かに頭をさげた。
私も、合掌。
孫をうながして外に出た私は、澄み渡るプノンペンの夜空を仰いでふと大きく呼吸を吸った。
陽気な孫も、ただ黙って私をみつめるだけだった。
<ジャポンの船長さんよ、早く来て、あなたの〝お蝶さん〟をなぐさめてやりなさいよ>
カンボジアは貧しい国、そして人々は素ぼくで、遠慮深い。子供は愛らしく、若い娘はかれんで美しい。
青年たちは、おだやかで、礼儀正しい。
私は、そんな国で罪深い所業は犯すまいと心に誓った。
2カ月後、日本に帰って、そのまま包み隠さず報告したら、カミさんは疑い深そうな目つきで私の顔を見て「あなた! 本当ですか」とぬかしよった。
カンボジアの首都、プノンぺン市内にはざっと600のシクロ(三輪タクシー)がある。
その運転手(といっても、自分で一生けんめいペダルを踏むドライバーだが…)の人に、孫という中国系カンボジア人がいた。
孫は、私の顔を見ると、どこまでも遠慮深げについて回った。私もつい情に負けて、毎日孫のシクロを専用に使うことになった。
ある晩、国際電信電報局へ出かけた帰り、孫がしきりにある女の所に寄ってくれと頼んだ。
「マスター、その女、かわいそう。ジャポンのキャプテン(船長さん)帰ってくるいって帰ってこない。女、かわいそう。
マスター、1度見る。よいか
カタコトの日本語と英語をごっちゃまぜにして、孫はこんな風に私をくどく。
前にのべたように、私は情にもろい。
やむを得ず、孫のいうままに、女のアパートを訪れた。
ご存じのように、カンボジアは元フランスの植民地。アパートはウナギの寝床のように長く、奥行が深い。
案内された女の部屋に着くまで、左右に3つ、4つ部屋がある。そのとき左の部屋の1つから赤ん坊の泣き声が聞えた。
私は、ハッと胸をつかれた。女は子供を抱えているのか。そのとたん、日本に残してきた娘の顔がちらと胸に浮んだ。
「マスター、マスター」孫の呼び声。
私は粗末な部屋の中央に、白っぼいアオザイ(両ワキの切れた中国風のドレス)を着た小さな女を見た。25。6歳か
両手を合わせ、静かな物腰で頭をさげる。
私も同じように手を合わせ、挨拶を返す。
小乗仏教の国カンボジアでは、こんな風に挨拶をするのだ。
孫が、ポン引よろしく私を誘う。
「マスター、この女かわいそう。おカネない。キャプテン、ノーカムバックウソついた。女、悲しいよ」
よくよく聞くと、まさに現代版お蝶夫人だ。
プノンペン市内にあるフランス系病院に勤める女は、月にわずか700リエールの給料をもらっているが、これではいかに物価が安いカンボジアでも苦しい1ドル(360円)は、公定ルートで35リエール、ヤミ値になると60リエールぐらいになる。つまり月給は4,000円足らずなのだ。
そこで、たまたまプノンペンの港に入ってきた日本の貨物船の船長が、現地妻としてこの女を囲った。やさしい船長さんだったようで、女は楽しい数週間を送った。船出の日がやってきたキャプテンはいった。
「かならず帰ってくるから、待っていてくれ」
女は、だまってジャポンの船長さんを見送った。
それから1年、キャプテンを待ちわびる女のせつない気持は、深まるばかりだが、いとしの君は、一向にやってこない。
かわって現れたのが、孫に連れられた私というわけだ。
うらさびしい表情。痛々しい様子。
私は胸がつまった。それでなくてもさっきの赤ん坊の泣き声で、私は聖僧のような境地である。
孫を通じて、私はこう伝えた。
「あなたの苦しい状態はよくわかります。しかし、私はいまおカネであなたと取引するような気持にはとてもなれない。このまま帰ります。許してください」
女は、悲しそうに目を伏せ、ふたたび合掌して静かに頭をさげた。
私も、合掌。
孫をうながして外に出た私は、澄み渡るプノンペンの夜空を仰いでふと大きく呼吸を吸った。
陽気な孫も、ただ黙って私をみつめるだけだった。
<ジャポンの船長さんよ、早く来て、あなたの〝お蝶さん〟をなぐさめてやりなさいよ>
カンボジアは貧しい国、そして人々は素ぼくで、遠慮深い。子供は愛らしく、若い娘はかれんで美しい。
青年たちは、おだやかで、礼儀正しい。
私は、そんな国で罪深い所業は犯すまいと心に誓った。
2カ月後、日本に帰って、そのまま包み隠さず報告したら、カミさんは疑い深そうな目つきで私の顔を見て「あなた! 本当ですか」とぬかしよった。
月刊ボディビルディング1969年7月号
Recommend
-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!
- BESTBODY JAPAN
- BESTBODY JAPAN Vol.2
- 金額: 1,527 円(税込)
-



























