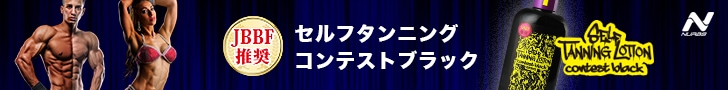ボディビルディングの革命理論≪その5≫
デニス・デュブライルの理論
月刊ボディビルディング1979年6月号
掲載日:2018.11.26
国立競技場指導係主任 矢野雅知
<すべての筋肉を十分に刺激するめには>
アーサー・ジョーンズをはじめとする多くの権威者は、各ボディ・パートには、十分な刺激を与えられるセット数さえ行なえば、1種目のエクササイズをやるだけで十分である、という。
たとえば上腕二頭筋にはスタンディング・バーベル・カールの1種目を行なえばよいというのである。
初期におけるアーノルド・シュワルツェネガーは、上腕屈筋の運動としては、ほとんどスタンディング・バーベル・カールだけをやっていた。
そして、19才で彼が国際舞台に初めて登場したときすでに腕の太さがセンセーションを巻き起したほど発達していたのである。
この例をみるならば、一つのボディ・パートには、十分なセット数を行な1種目のエクササイズでよい、と考えられるかもしれない。
確かに、競技スポーツの選手として上腕屈筋を鍛えるためには、ふつうの基本的エクササイズを行なうことで十分な効果を得られるだろう。
フットボール選手や水泳選手等が、上腕屈筋の運動のためにウォール・カール、ハンギング・カール、あるいはゾットマン・エクササイズなどの、何種類ものエクササイズを行なうことは、ほとんどない。
だがしかし、ボディビルダーは、筋肉の実質的な発達と同時に、外見上の「美」を極限まで追求することを第一義としている。したがって、筋肉をあらゆる角度から鍛え込み、全身の筋肉すべてを発達させて、なおかつそこに調和を保たねばならないのである。
この目的を達成するのに、基本的エクササイズだけで十分であろうか。
サージ・レディングという、とてつもなく太い腕を持つビルダーがいる。
彼の腕はたしかに太い。だが、その上腕屈筋は奇妙に思えるほど巾が狭い。狭いだけでなく、筋肉が盛り上っているのはその中央部だけなのである。
これは、彼がプーリー・ウェイトを用いてハーフ・レインジのカールを徹底的にやったからである。筋肉の中央部は発達しても、上腕屈筋全体の発達が十分でないことになる。
また、サム・アップ・カールをやれば、下部および中央部が集中的に刺激されるというように、「ほとんどのエクササイズが、1つのボディ・パートすべての筋線維に、十分な刺激を与えられるものはない」からである。
だから、ボディビルダーの第一義とする、パーフェクトに筋肉が発達した「完成美」を求めるには、多くのエクササイズをやらなくてはならないのである。
確かにシュワルツェネガーの上腕屈筋を発達させた基本的エクササイズは、スタンディング・バーベル・カールであったが、サイズの大きさだけでミスター・オリンピアまでのぼりつめることは出来ない。
米国で修業するようになってから、彼はありとあらゆるエクササイズを採用して、あらゆる角度から筋肉に刺激を与えていったからあの巾広く素晴らしいピークをもった上腕屈筋をつくりあげたのである。
神様ジョン・C・グリメックは述べている。
「一つのエクササイズを10セット行なうよりも、10の異なったエクササイズを1セットずつ行なうべきである」
これこそ、より多くの筋線維を働かせる秘訣であるかもしれない。
この達見があったからこそ、グリメックはパーフェクトなシンメトリーとあの発達した肉体をつくりあげ得たのであり、40才を超えてもなおかつスティーブ・リーブス、クラレンス・ロスといった強豪を、その牙城に一歩も近づけることなく、無敗のまま引退したのであろう。
たとえば上腕二頭筋にはスタンディング・バーベル・カールの1種目を行なえばよいというのである。
初期におけるアーノルド・シュワルツェネガーは、上腕屈筋の運動としては、ほとんどスタンディング・バーベル・カールだけをやっていた。
そして、19才で彼が国際舞台に初めて登場したときすでに腕の太さがセンセーションを巻き起したほど発達していたのである。
この例をみるならば、一つのボディ・パートには、十分なセット数を行な1種目のエクササイズでよい、と考えられるかもしれない。
確かに、競技スポーツの選手として上腕屈筋を鍛えるためには、ふつうの基本的エクササイズを行なうことで十分な効果を得られるだろう。
フットボール選手や水泳選手等が、上腕屈筋の運動のためにウォール・カール、ハンギング・カール、あるいはゾットマン・エクササイズなどの、何種類ものエクササイズを行なうことは、ほとんどない。
だがしかし、ボディビルダーは、筋肉の実質的な発達と同時に、外見上の「美」を極限まで追求することを第一義としている。したがって、筋肉をあらゆる角度から鍛え込み、全身の筋肉すべてを発達させて、なおかつそこに調和を保たねばならないのである。
この目的を達成するのに、基本的エクササイズだけで十分であろうか。
サージ・レディングという、とてつもなく太い腕を持つビルダーがいる。
彼の腕はたしかに太い。だが、その上腕屈筋は奇妙に思えるほど巾が狭い。狭いだけでなく、筋肉が盛り上っているのはその中央部だけなのである。
これは、彼がプーリー・ウェイトを用いてハーフ・レインジのカールを徹底的にやったからである。筋肉の中央部は発達しても、上腕屈筋全体の発達が十分でないことになる。
また、サム・アップ・カールをやれば、下部および中央部が集中的に刺激されるというように、「ほとんどのエクササイズが、1つのボディ・パートすべての筋線維に、十分な刺激を与えられるものはない」からである。
だから、ボディビルダーの第一義とする、パーフェクトに筋肉が発達した「完成美」を求めるには、多くのエクササイズをやらなくてはならないのである。
確かにシュワルツェネガーの上腕屈筋を発達させた基本的エクササイズは、スタンディング・バーベル・カールであったが、サイズの大きさだけでミスター・オリンピアまでのぼりつめることは出来ない。
米国で修業するようになってから、彼はありとあらゆるエクササイズを採用して、あらゆる角度から筋肉に刺激を与えていったからあの巾広く素晴らしいピークをもった上腕屈筋をつくりあげたのである。
神様ジョン・C・グリメックは述べている。
「一つのエクササイズを10セット行なうよりも、10の異なったエクササイズを1セットずつ行なうべきである」
これこそ、より多くの筋線維を働かせる秘訣であるかもしれない。
この達見があったからこそ、グリメックはパーフェクトなシンメトリーとあの発達した肉体をつくりあげ得たのであり、40才を超えてもなおかつスティーブ・リーブス、クラレンス・ロスといった強豪を、その牙城に一歩も近づけることなく、無敗のまま引退したのであろう。

シュワルツェネッガーは、ボディビルディング開始当初、腕の運動といえばもっぱらスタンディング・バーベル・カールだけだったという
<フル・レインジ・エクササイズの重要性>
ほとんどの運動生理学者やトレーナーは「トレーニングにおいては、できるだけ可動範囲いっぱいやるためにフル・レインジのエクササイズをやらなくてはならない」という。
それは、筋肉をバランスよく完全に発達させるためで、そうしないと柔軟性の低下をきたすことになるからである。
フル・レインジの運動を正しく行なっていれば、ウェイト・トレーニングは誤解されるようなマッスル・バウンドに陥いることは絶対にない、ということはすでに証明されている。
いやむしろ、可動範囲いっぱいに動かすことによって、柔軟性は高まることにもなるのである。
それでも、たとえばパーシャル・レインジ・カールを行なうならば、そのあとで必ずフル・レインジのカールをやるようにして、筋肉がマッスル・バウンドに陥いることを防ぐようにしなくてはならないであろう。
それを無視して、パーシャル・レインジの動きばかりをズーッと続けていると———たとえば、鍛治屋のスミスなんぞは、朝から晩までヒジを曲げたまんまでトンチン、カンチンやっているものだから、ついにはヒジがひん曲ったままになってしまい、典型的なマッスル・バウンドになってしまうのである。
もっとも、パージャル・レインジの運動というものは、筋肉の可動範囲全般にわたって刺激しないで、筋肉の一部分を太く強くしてゆくから、「筋力」を得るには、たいへん便利な方法である。
ところで、ウェイト・リフターは、肩関節の柔軟性が大きくないと、スナッチなどの種目では正しいフォームでウェイトを差し上げることが困難になってしまう。
ところが彼らは、ベンチ・プレスをあまりやり過ぎると、大切な肩関節がカタくなることに気がついた。
それは、ベンチ・プレスが肩の筋肉にとっては、フル・レインジ・ムーブメントではないからである。腕は背中の後ろまで十分に下げられるから、大きなムーブメントになるが、バーは胸の上に止まってしまうので、肩はフル・レインジの運動とはならないのである。
(しかし、このことは他のスポーツマンにとってはさほど問題にしなくてもだいじょうぶ。大いにベンチ・プレスをやるべきである)。
そこで、
「すべての筋線維を刺激して、柔軟性の低下を避けるための方法は、フル・レインジ・エクササイズを行なうことである」
ということになるが、これは正しいであろうか?———実は、正しいとは言えないのである。
そもそも腕や脚を鍛えるフル・レインジ・エクササイズなんぞというものはない。
そう、確かに我々は、スタンディング・カールなどを行なうときに、腕を十分に伸ばした姿勢から、バーベルを肩の方まで巻き上げてきて、十分に上腕屈筋を収縮しているはずである。
ところがこれは、完全なフル・レインジ・エクササイズではないのである。
上腕二頭筋には三つの機能がある。それは、腕を曲げる。ねじる。そして肩での挙上動作を助けるといったものである。
三番目の機能について説明すると、スタンディング・プレスなどを行なう場合、肩にバーベルをおいたスタート姿勢のときに、上腕二頭筋がときおり痛みを感じるのは、このとき働いているからである。
これらのことを念頭に置いて、上腕二頭筋のフル・レインジについて説明しよう。
からだの後ろに腕をもってくる———
ちょうどトライセプス・キック・バックの動作をやり終えたようなポジション———そのとき腕を十分に伸ばして、しかもリバース・カールをやるように「手」を内側に反転(ねじる)する。
このとき、“これだけが、上腕二頭筋にとっては、完全に伸展されたポジション”なのである。たとえば、ライイング・ダウン・カールなどをやると、このポジションをとれることになる。
そして、肘を曲げて、その肘をできるだけ高く頭上に持ち上げて、ふつうのカールを行なうグリップの位置になるように「手」を反対側にターンしたとき———ちょうどトライセプス・プレスをリバース・グリップでスタートする姿勢のとき——このとき、“これだけが、完全に収縮したポジション”である。
これら2つの、完全なる伸展のポジションと収縮のポジションを伴なうというエクササイズはない。
したがって上腕二頭筋には、フル・レインジ・エクササイズも、それを可能にするマシーンなどというものも、ないことになる。
たとえあるとしても、それは「上腕二頭筋and肩」のマシーンということになる。なぜなら、肩の筋肉を働かせずに、腕を頭上に持ち上げることはできないからである。
アーサー・ジョーンズは「ノーチラス・マシーンは、フル・レインジ・エクササイズができる」という点を大いに強調しており、「だから大きな効果が期待できる」としている。
確かにノーチラス・マシーンは大きな可動範囲で運動できるように考案されているが上述のように、それは完全なフル・レインジ・エクササイズではないことがおわかりいただけよう。
さて、脚の筋肉であるが、これも同様である。大腿二頭筋を鍛えるためには、主にレッグカール・マシーンを使用するが、これでヒザを曲げて筋肉を最大限に収縮させるためには、大腿部と上体は一直線になっていなくてはならない。
そしてヒザを伸ばして、大腿二頭筋を最大に伸展させるためには、上体をできるだけ前屈させなくてはならないのである。
つまり、脚を直っすぐ伸ばして立った姿勢から、上体を曲げて足先に手を触れるように前屈させたポジションである。
これも、一連の動きを1つのエクササイズで可能にするものはない。
そこで次のような結論に到達することになる。
「最も完全な筋肉の発達を望むのであるならば、完全に伸ばし切ったポジションを与えるエクササイズと、完全に収縮したポジションを与えるエクササイズの、両方のものをやらなくてはならない」
また、これらのエクササイズを行なうなルーティンに組み立てれば、柔軟性も完全な発達を示すことになろう。
以上のことからも、1つのボディ・パートに1つのエクササイズだけでは完全な筋肉の発達は望めない、ということがわかるであろう。
筋肉全てに刺激を与えるには、多くのエクササイズが必要とされるのである。
老姿心ながら、ここでは柔軟性の低下を避けるようにと強調しているが、大きな柔軟性を必要とするスポーツ選手を除けば、ほとんどの人々にとっ柔軟性の少しぐらいの低下は、たいした妨げとはならない。
たとえば、今は全国的にジョッギング・ブームであり、走ることのみを生きがいとしている人も少なくないが、ランニングそのものは、筋肉の可動範囲が大きくないので、そればかり行なっていると、当然柔軟性が失われることが考えられる。
しかし、ジョギングを愛好している人にとっては、そんなことはさほど重要な問題とはならないであろう。
したがって、マッスル・バウンドの迷信などは、吹き飛ばしてしまった方がよいだろう。
それは、筋肉をバランスよく完全に発達させるためで、そうしないと柔軟性の低下をきたすことになるからである。
フル・レインジの運動を正しく行なっていれば、ウェイト・トレーニングは誤解されるようなマッスル・バウンドに陥いることは絶対にない、ということはすでに証明されている。
いやむしろ、可動範囲いっぱいに動かすことによって、柔軟性は高まることにもなるのである。
それでも、たとえばパーシャル・レインジ・カールを行なうならば、そのあとで必ずフル・レインジのカールをやるようにして、筋肉がマッスル・バウンドに陥いることを防ぐようにしなくてはならないであろう。
それを無視して、パーシャル・レインジの動きばかりをズーッと続けていると———たとえば、鍛治屋のスミスなんぞは、朝から晩までヒジを曲げたまんまでトンチン、カンチンやっているものだから、ついにはヒジがひん曲ったままになってしまい、典型的なマッスル・バウンドになってしまうのである。
もっとも、パージャル・レインジの運動というものは、筋肉の可動範囲全般にわたって刺激しないで、筋肉の一部分を太く強くしてゆくから、「筋力」を得るには、たいへん便利な方法である。
ところで、ウェイト・リフターは、肩関節の柔軟性が大きくないと、スナッチなどの種目では正しいフォームでウェイトを差し上げることが困難になってしまう。
ところが彼らは、ベンチ・プレスをあまりやり過ぎると、大切な肩関節がカタくなることに気がついた。
それは、ベンチ・プレスが肩の筋肉にとっては、フル・レインジ・ムーブメントではないからである。腕は背中の後ろまで十分に下げられるから、大きなムーブメントになるが、バーは胸の上に止まってしまうので、肩はフル・レインジの運動とはならないのである。
(しかし、このことは他のスポーツマンにとってはさほど問題にしなくてもだいじょうぶ。大いにベンチ・プレスをやるべきである)。
そこで、
「すべての筋線維を刺激して、柔軟性の低下を避けるための方法は、フル・レインジ・エクササイズを行なうことである」
ということになるが、これは正しいであろうか?———実は、正しいとは言えないのである。
そもそも腕や脚を鍛えるフル・レインジ・エクササイズなんぞというものはない。
そう、確かに我々は、スタンディング・カールなどを行なうときに、腕を十分に伸ばした姿勢から、バーベルを肩の方まで巻き上げてきて、十分に上腕屈筋を収縮しているはずである。
ところがこれは、完全なフル・レインジ・エクササイズではないのである。
上腕二頭筋には三つの機能がある。それは、腕を曲げる。ねじる。そして肩での挙上動作を助けるといったものである。
三番目の機能について説明すると、スタンディング・プレスなどを行なう場合、肩にバーベルをおいたスタート姿勢のときに、上腕二頭筋がときおり痛みを感じるのは、このとき働いているからである。
これらのことを念頭に置いて、上腕二頭筋のフル・レインジについて説明しよう。
からだの後ろに腕をもってくる———
ちょうどトライセプス・キック・バックの動作をやり終えたようなポジション———そのとき腕を十分に伸ばして、しかもリバース・カールをやるように「手」を内側に反転(ねじる)する。
このとき、“これだけが、上腕二頭筋にとっては、完全に伸展されたポジション”なのである。たとえば、ライイング・ダウン・カールなどをやると、このポジションをとれることになる。
そして、肘を曲げて、その肘をできるだけ高く頭上に持ち上げて、ふつうのカールを行なうグリップの位置になるように「手」を反対側にターンしたとき———ちょうどトライセプス・プレスをリバース・グリップでスタートする姿勢のとき——このとき、“これだけが、完全に収縮したポジション”である。
これら2つの、完全なる伸展のポジションと収縮のポジションを伴なうというエクササイズはない。
したがって上腕二頭筋には、フル・レインジ・エクササイズも、それを可能にするマシーンなどというものも、ないことになる。
たとえあるとしても、それは「上腕二頭筋and肩」のマシーンということになる。なぜなら、肩の筋肉を働かせずに、腕を頭上に持ち上げることはできないからである。
アーサー・ジョーンズは「ノーチラス・マシーンは、フル・レインジ・エクササイズができる」という点を大いに強調しており、「だから大きな効果が期待できる」としている。
確かにノーチラス・マシーンは大きな可動範囲で運動できるように考案されているが上述のように、それは完全なフル・レインジ・エクササイズではないことがおわかりいただけよう。
さて、脚の筋肉であるが、これも同様である。大腿二頭筋を鍛えるためには、主にレッグカール・マシーンを使用するが、これでヒザを曲げて筋肉を最大限に収縮させるためには、大腿部と上体は一直線になっていなくてはならない。
そしてヒザを伸ばして、大腿二頭筋を最大に伸展させるためには、上体をできるだけ前屈させなくてはならないのである。
つまり、脚を直っすぐ伸ばして立った姿勢から、上体を曲げて足先に手を触れるように前屈させたポジションである。
これも、一連の動きを1つのエクササイズで可能にするものはない。
そこで次のような結論に到達することになる。
「最も完全な筋肉の発達を望むのであるならば、完全に伸ばし切ったポジションを与えるエクササイズと、完全に収縮したポジションを与えるエクササイズの、両方のものをやらなくてはならない」
また、これらのエクササイズを行なうなルーティンに組み立てれば、柔軟性も完全な発達を示すことになろう。
以上のことからも、1つのボディ・パートに1つのエクササイズだけでは完全な筋肉の発達は望めない、ということがわかるであろう。
筋肉全てに刺激を与えるには、多くのエクササイズが必要とされるのである。
老姿心ながら、ここでは柔軟性の低下を避けるようにと強調しているが、大きな柔軟性を必要とするスポーツ選手を除けば、ほとんどの人々にとっ柔軟性の少しぐらいの低下は、たいした妨げとはならない。
たとえば、今は全国的にジョッギング・ブームであり、走ることのみを生きがいとしている人も少なくないが、ランニングそのものは、筋肉の可動範囲が大きくないので、そればかり行なっていると、当然柔軟性が失われることが考えられる。
しかし、ジョギングを愛好している人にとっては、そんなことはさほど重要な問題とはならないであろう。
したがって、マッスル・バウンドの迷信などは、吹き飛ばしてしまった方がよいだろう。
<レピティションについて>
ある権威は「大きな筋肉にさせたいと思うならば、より多くのレピティションとセット数が必要となる」と、主張している。
この考え方に基づいてトレーニングを行なって、それによって十分な効果を示している人もいる。
だが、トレーニングは、筋肉の発達レベルが高ければ高いほど、より多くのトレーニング量をやればよい、というものではない。
アーサー・ジョーンズなどが主張するように、トレーニングの量よりも質の高いことがより以上に重要なファクターなのである。
ところで、筋肉を発達させるのに必要なトレーニングの量というものは、各筋肉によって違いがある、ということを知っておく必要があるだろう。
ある筋肉は、他の筋肉よりもさらに多くのレピティションをやらなくてはならないという根拠は、しごく簡単なことである。
筋肉によっては、コントロールさせやすいものがあるが、それは1回の収縮で、非常に多くの筋線維を働かせることができるからである。これには、運動単位が関与している。
つまり、脳のシグナルは、運動神経を通して各筋線維に伝わるわけだが、1つの運動神経は何本もの筋線維につながっていてこれを支配している。
これを運動単位あるいは神経筋単位と呼んでいる。
たとえば、複雑なコントロールができる外眼筋は、1本の神経がわずか3本の筋線維につながって1つの運動単位となっているが、大腿部の運動単位では100本の筋線維となっている。
また、手の指の運動単位は100本の筋線維をもっているが、カーフの筋肉では1本の運動神経で2000本もの筋線維を支配している。
だから、我々はカーフよりも指の方がずっとコントロールしやすいことになる。それは、1回のレピティションで多くの筋線維を活動させやすいからである。
このことから、腕よりも脚の筋肉の方が1回で筋線維の多くを活動できないから、当然レピティションも多くしなくてはならない。
また、足でも大腿部よりも下腿の方が、より以上に多くのレピティションが必要とされることになる。
たとえば、上腕二頭筋のトレーニングには、1セットあたり10回でほとんどの筋線維に刺激を与えることができても、カーフのトレーニングでは、1セットあたり20回以上やらないと、筋肉すべてに刺激を与えることができないということなのである。
(つづく)
この考え方に基づいてトレーニングを行なって、それによって十分な効果を示している人もいる。
だが、トレーニングは、筋肉の発達レベルが高ければ高いほど、より多くのトレーニング量をやればよい、というものではない。
アーサー・ジョーンズなどが主張するように、トレーニングの量よりも質の高いことがより以上に重要なファクターなのである。
ところで、筋肉を発達させるのに必要なトレーニングの量というものは、各筋肉によって違いがある、ということを知っておく必要があるだろう。
ある筋肉は、他の筋肉よりもさらに多くのレピティションをやらなくてはならないという根拠は、しごく簡単なことである。
筋肉によっては、コントロールさせやすいものがあるが、それは1回の収縮で、非常に多くの筋線維を働かせることができるからである。これには、運動単位が関与している。
つまり、脳のシグナルは、運動神経を通して各筋線維に伝わるわけだが、1つの運動神経は何本もの筋線維につながっていてこれを支配している。
これを運動単位あるいは神経筋単位と呼んでいる。
たとえば、複雑なコントロールができる外眼筋は、1本の神経がわずか3本の筋線維につながって1つの運動単位となっているが、大腿部の運動単位では100本の筋線維となっている。
また、手の指の運動単位は100本の筋線維をもっているが、カーフの筋肉では1本の運動神経で2000本もの筋線維を支配している。
だから、我々はカーフよりも指の方がずっとコントロールしやすいことになる。それは、1回のレピティションで多くの筋線維を活動させやすいからである。
このことから、腕よりも脚の筋肉の方が1回で筋線維の多くを活動できないから、当然レピティションも多くしなくてはならない。
また、足でも大腿部よりも下腿の方が、より以上に多くのレピティションが必要とされることになる。
たとえば、上腕二頭筋のトレーニングには、1セットあたり10回でほとんどの筋線維に刺激を与えることができても、カーフのトレーニングでは、1セットあたり20回以上やらないと、筋肉すべてに刺激を与えることができないということなのである。
(つづく)
月刊ボディビルディング1979年6月号
Recommend
-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!
- BESTBODY JAPAN
- BESTBODY JAPAN Vol.2
- 金額: 1,527 円(税込)
-