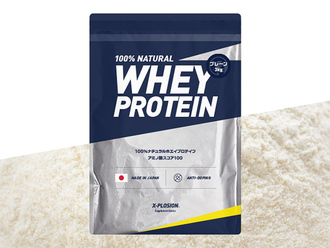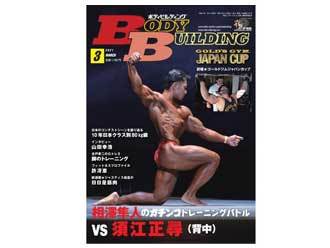高頻度トレーニングの導入がうまくいかない場合
掲載日:2017.08.30

導入がうまくいかない場合
高頻度トレーニングに適応できる人の場合、大体2カ月程度の短い期間で導入期間が終了し、高頻度トレーニングに適応できる体を作ることができます。
ただし、全ての人が2カ月という短い期間で適応できるわけではありません。適応までにもっと長い期間を要する人もいますし、いつまでたっても適応できない人もいます。
こういったときの主な理由として、「トレーニング内容に問題がある」ということがあげられますが、中には根本的に「高頻度トレーニングに向いていない」ということもあります。
トレーニング内容に問題がある場合
トレーニング内容に問題があるということが、高頻度トレーニングがうまく導入できない一番の理由となります。
トレーニング内容に問題があると、どうしても疲労がたまりやすくなり、導入が難しくなってきます。メイントレーニングに関しては、通常は基本的なトレーニング方法の範囲内のトレーニングを行うことが多いため、それほど問題は出ません。
しかし、サブトレーニングは回復に時間のかかる体を作るトレーニングを中心に行うこと、トレーニングにオフを取るということから、知らないうちにトレーニングを頑張りすぎてしまい、疲労がたまって回復が追いつかなくなるということが起こりやすくなっています。
回復が追い付かない場合は、サブトレーニングのトレーニング内容を回復が間に合う内容に変更し、同時に疲労を抜くためのオフを設け、その後に一定の重量を下げて改めて高頻度トレーニングの導入をやり直すことになります。
サブトレーニングのトレーニング内容の変更方法として最初に行うべきなのが、「補助種目をなくす」ことです。
サブトレーニングでは次の日がオフになるため、どうしてもメインセット後に補助種目を頑張りすぎてしまう事が多くなります。
しかし、補助種目を頑張りすぎてしまうと回復が追いつかなくなり、肝心のメインセットでセットクリアできなくなってしまいます。
あくまで、補助種目は補助であり、メインセットでクリアしていくことが重要なので、このような場合は補助種目を行わないようにし、メインセットだけを行うようにします。
補助種目を行わなくなっても(最初から補助種目を行っていなくても)疲労がたまり、導入がうまくいかない場合に行うのが、サブトレーニングの「メインセットのトレーニング内容を変更する」ことです。
変更方法としては、単純にセット数を3セットから2セットといったように本来のセット数を減らす方法、やり直しでのセット数とセットクリア条件の難度の上げ幅を少なくする方法、回数やセット数を変えてトレーニングの目的を変える方法などがあります。
サブトレーニングのメインセットのトレーニング内容を変更しても導入がうまくいかない場合に、最後の手段となるトレーニング内容の変更方法が、「メインセットをなくして補助種目だけを行う」ことです。
本来、高頻度トレーニングではメイントレーニングとサブトレーニングの両方でベンチプレスのトレーニングを行い、導入部分ではメイントレーニングとサブトレーニングの両方でやり直しを活用し、少しずつ身体を高頻度トレーニングに適応させていきます。
しかし、中にはベンチプレスのトレーニングだけを高頻度で行う事はできないが、ベンチブレスに関係する筋肉を鍛える補助種目のトレーニングを織り交ぜれば、高頻度でトレーニングを行なえるという人がいます。
こういった人の場合、メイントレーニングの日にだけやり直しを活用しながらベンチプレスを行い、サブトレーニングの日にはベンチプレスを行わず、補助種目だけを通常のトレーニング通りに行うようにします。
トレーニングの内容を変更する場合、特にサブトレーニングのトレーニング内容を変更し、「補助種目をなくす」「メインセットのトレーニング内容を変更する」「メインセットをなくして補助種目だけを行う」の順に変更を行っていくわけですが、いずれの変更後も3日から1週間のオフを取って疲労をある程度除き、その後にメイントレーニングとサブトレーニングともにある程度重量を下げて、改めてやり直しを活用した高頻度トレーニングの導入を再開します。
サブトレーニングのトレーニング内容を変更した際の重量の下げ幅は、メイントレーニングはいずれの場合も現在扱っている重量-5kg~-10kg。
サブトレーニングは、補助種目をなくす場合は現在扱っている重量-5kg~10kg。サブトレーニングのメインセットのトレーニング内容を変更する場合の、セット数やセットクリア条件の難度の上げ幅を増やす、難度を上げないようにするといった、比較的少ない変更の場合は-5kg~-10kg。トレーニングの目的を変えるほどの大きな変更の場合はセットベスト-22.5kgの最初の設定重量まで下げるようにします。
なお、サブトレーニングのトレーニング内容を変更するタイミングの目安としては、以下の3つがあります。
①メイントレーニングサブトレーニングのセット重量がセットベスト-10㎏程度の導入期前半でセットクリアに手間取る、またはセットクリアできない場合
②2週間同じ重量でトレーニングを行っていて、今よりも挙がる気配が全く無い場合
③疲労により明らかに調子が落ちてきた場合
あくまで大まかな目安ですが、このような状態に陥ったときはサブトレーニングのトレーニング内容を変更し、重量を下げたうえで高頻度トレーニングの導入を再開することになります。
高頻度トレーニングに適応できる人の場合、大体2カ月程度の短い期間で導入期間が終了し、高頻度トレーニングに適応できる体を作ることができます。
ただし、全ての人が2カ月という短い期間で適応できるわけではありません。適応までにもっと長い期間を要する人もいますし、いつまでたっても適応できない人もいます。
こういったときの主な理由として、「トレーニング内容に問題がある」ということがあげられますが、中には根本的に「高頻度トレーニングに向いていない」ということもあります。
トレーニング内容に問題がある場合
トレーニング内容に問題があるということが、高頻度トレーニングがうまく導入できない一番の理由となります。
トレーニング内容に問題があると、どうしても疲労がたまりやすくなり、導入が難しくなってきます。メイントレーニングに関しては、通常は基本的なトレーニング方法の範囲内のトレーニングを行うことが多いため、それほど問題は出ません。
しかし、サブトレーニングは回復に時間のかかる体を作るトレーニングを中心に行うこと、トレーニングにオフを取るということから、知らないうちにトレーニングを頑張りすぎてしまい、疲労がたまって回復が追いつかなくなるということが起こりやすくなっています。
回復が追い付かない場合は、サブトレーニングのトレーニング内容を回復が間に合う内容に変更し、同時に疲労を抜くためのオフを設け、その後に一定の重量を下げて改めて高頻度トレーニングの導入をやり直すことになります。
サブトレーニングのトレーニング内容の変更方法として最初に行うべきなのが、「補助種目をなくす」ことです。
サブトレーニングでは次の日がオフになるため、どうしてもメインセット後に補助種目を頑張りすぎてしまう事が多くなります。
しかし、補助種目を頑張りすぎてしまうと回復が追いつかなくなり、肝心のメインセットでセットクリアできなくなってしまいます。
あくまで、補助種目は補助であり、メインセットでクリアしていくことが重要なので、このような場合は補助種目を行わないようにし、メインセットだけを行うようにします。
補助種目を行わなくなっても(最初から補助種目を行っていなくても)疲労がたまり、導入がうまくいかない場合に行うのが、サブトレーニングの「メインセットのトレーニング内容を変更する」ことです。
変更方法としては、単純にセット数を3セットから2セットといったように本来のセット数を減らす方法、やり直しでのセット数とセットクリア条件の難度の上げ幅を少なくする方法、回数やセット数を変えてトレーニングの目的を変える方法などがあります。
サブトレーニングのメインセットのトレーニング内容を変更しても導入がうまくいかない場合に、最後の手段となるトレーニング内容の変更方法が、「メインセットをなくして補助種目だけを行う」ことです。
本来、高頻度トレーニングではメイントレーニングとサブトレーニングの両方でベンチプレスのトレーニングを行い、導入部分ではメイントレーニングとサブトレーニングの両方でやり直しを活用し、少しずつ身体を高頻度トレーニングに適応させていきます。
しかし、中にはベンチプレスのトレーニングだけを高頻度で行う事はできないが、ベンチブレスに関係する筋肉を鍛える補助種目のトレーニングを織り交ぜれば、高頻度でトレーニングを行なえるという人がいます。
こういった人の場合、メイントレーニングの日にだけやり直しを活用しながらベンチプレスを行い、サブトレーニングの日にはベンチプレスを行わず、補助種目だけを通常のトレーニング通りに行うようにします。
トレーニングの内容を変更する場合、特にサブトレーニングのトレーニング内容を変更し、「補助種目をなくす」「メインセットのトレーニング内容を変更する」「メインセットをなくして補助種目だけを行う」の順に変更を行っていくわけですが、いずれの変更後も3日から1週間のオフを取って疲労をある程度除き、その後にメイントレーニングとサブトレーニングともにある程度重量を下げて、改めてやり直しを活用した高頻度トレーニングの導入を再開します。
サブトレーニングのトレーニング内容を変更した際の重量の下げ幅は、メイントレーニングはいずれの場合も現在扱っている重量-5kg~-10kg。
サブトレーニングは、補助種目をなくす場合は現在扱っている重量-5kg~10kg。サブトレーニングのメインセットのトレーニング内容を変更する場合の、セット数やセットクリア条件の難度の上げ幅を増やす、難度を上げないようにするといった、比較的少ない変更の場合は-5kg~-10kg。トレーニングの目的を変えるほどの大きな変更の場合はセットベスト-22.5kgの最初の設定重量まで下げるようにします。
なお、サブトレーニングのトレーニング内容を変更するタイミングの目安としては、以下の3つがあります。
①メイントレーニングサブトレーニングのセット重量がセットベスト-10㎏程度の導入期前半でセットクリアに手間取る、またはセットクリアできない場合
②2週間同じ重量でトレーニングを行っていて、今よりも挙がる気配が全く無い場合
③疲労により明らかに調子が落ちてきた場合
あくまで大まかな目安ですが、このような状態に陥ったときはサブトレーニングのトレーニング内容を変更し、重量を下げたうえで高頻度トレーニングの導入を再開することになります。
[ ベンチプレス 基礎から実践 ベンチプレスが誰よりも強くなる(VOL.1) ]
Recommend
-

- 「ONE MORE REP」サポート!オールインワン プレワークアウトパウダー
- MPN
- 【MPN】HYPER PUMP NEO(ハイパーパンプ・ネオ) オレンジマンゴー風味
- 金額: 7,020 円(税込)
-